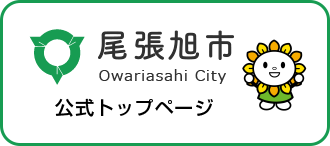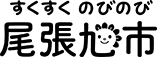本文
こどもの任意予防接種
以下の予防接種(任意接種)は、予防接種法に基づかない予防接種のため、接種費用は保護者負担となります。また、健康被害が発生した際は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済となります。接種に当たっては、接種医とよく相談のうえ、有効性とリスクを理解した上で受けてください。
インフルエンザ
インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。鼻水、くしゃみ、咳など一般的な風邪の症状に加えて、突然の38度以上の発熱や頭痛、関節痛、筋肉痛などの全身の症状が現れます。小児では、まれに急性脳症、高齢者や免疫力の低下している方では肺炎を伴うなど、重症になることがあります。日本では、インフルエンザは例年12月~3月が流行シーズンです。一方、新型コロナウイルス感染症の流行以降、インフルエンザの流行が過去と異なるタイミングで開始したという報告が見られています。
新型コロナウイルス感染症の位置づけが、令和5年5月8日に「5類感染症」に移行したことに伴い、令和2年度から令和4年度まで臨時的に実施した「お子さんや妊娠中の方等へのインフルエンザ予防接種の費用助成」はありません。
予防接種
インフルエンザワクチンは、「発病」や「重症化」「死亡」を予防することには、一定の効果があるといわれています。インフルエンザにかかると特に基礎疾患のある方や高齢の方では重症化する可能性が高いと考えられています。乳幼児のインフエルエンザワクチンの有効性に関しては、報告によって多少幅がありますが、概ね20~60%の発病防止効果があったと報告されています(※1、2)
(※1)平成14年度 厚生労働科学研究費補助金 新興・再興感染症研究事業「乳幼児に対するインフルエンザワクチンの効果に関する研究(研究代表者:神谷 齊(国立病院機構三重病院)・加地正郎(久留米大学))」
(※2) 平成28年度 厚生労働科学研究費補助金 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業「ワクチンの有効性・安全性評価とVPD (vaccine preventable diseases)対策への適用に関する分析疫学研究(研究代表者:廣田良夫(保健医療経営大学))
関連情報
・高齢者等インフルンエンザ予防接種はこちら(尾張旭市)
・インフルエンザ(総合ページ)厚生労働省<外部リンク>
おたふくかぜ
飛沫感染、接触感染により感染します。2週間から3週間の潜伏期間の後、耳下腺、顎下腺などの腫れと痛みを主な症状として発症します。髄膜炎、難聴、成人の精巣炎、卵巣炎などの合併症をおこすことがあります。治癒するまで、保育園、幼稚園、学校は出席停止となります。
予防接種の対象年齢は1歳以上で、2回接種がすすめられるようになってきました。現在、おたふくかぜワクチン予防接種の費用助成はありません。