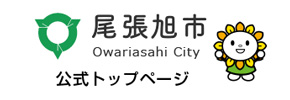本文
おわりあさひしのぼうのて
尾張旭市の棒の手
| 種別 | 無形民俗文化財(愛知県指定文化財第23号) |
|---|---|
| 指定年月日 |
昭和33年3月29日 旭町の棒の手、無形文化財指定 昭和51年7月14日 無形民俗文化財再指定 |
| 保存団体 | 尾張旭市棒の手保存会 |
棒の手は、棒や木太刀を使う武術的な民俗芸能で、2人から5人の演技者が型に従って演技を行います。五穀豊穣などを願う神事芸能として、また農民の自衛手段として受け継がれてきました。流派によって名称の違いはありますが、本来の棒や木太刀を使った神事的要素の強い「表」または「本手」といわれる型と、観衆を楽しませるためのキレモノ(真剣等)を使った「花棒」または「祭礼棒」といわれる型があります。
棒の手は、愛知県や岐阜県などにさまざまな流派が伝えられていますが、尾張旭市では無二流、検藤流、直心我流、東軍流及び直師夢想東軍流の5流派が伝統を守っています。
~無二流~
市内の旧新居村に伝わる流派です。南北朝時代に南朝方の僧将であった水野又太郎良春が正平十六(1361)年に新居村を開き、吉野金峰山寺の吉水院宗信法印から伝授された棒術を人々に教えたのが始まりといわれています。型や姿勢に厳しく、前に出す足は常に真っ直ぐです。多度神社に奉納されます。
~検藤流~
市内の旧稲葉村に伝わる流派です。稲葉村出身で柴田勝家の家臣となった毛受勝助家照の子孫、毛受周平が文化八(1811)年に村人に教えたのが始まりといわれています。棒術の基本は「棒対太刀」とされており、「ドコイ」のかけ声(気合)で演技を終了します。一之御前神社に奉納されます。
~直心我流~
旧印場村北部の浅見・朝見・森・矢木・寺尾などの姓の人々によって伝えられています。正徳四(1714)年、猪子石村の修験者比企良雄から棒を伝授された八木弥市郎博章が印場村に伝えたのが始まりといわれています。この流派は、早業が特徴。そのため演技速度も速く、演技時間や掛け声も短くなっています。渋川神社に奉納されます。
~東軍流~
旧印場村北部の斎場・塚本・寺尾などの姓の人々が中心となって伝えています。貞享元(1684)年、修験者だった伝昌院伝寿によって伝えられたといわれています。攻めを主体とした演技が多いのが特徴で、真剣を使った迫力ある演技でも知られています。渋川神社に奉納されます。
~直師夢想東軍流~
旧印場村南部、庄中地区を中心に伝えられた流派です。文政四(1821)年、出来町の蓬師範に学んだ森下理右衛門が開いたと伝えられています。衣装の股引が紺色なので、市内の流派が集まる祭りでもすぐに見分けることができます。渋川神社に奉納されます。
動画