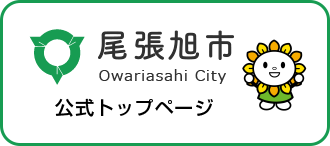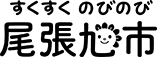本文
児童手当の概要
児童手当は、高校生年代までの児童を養育している方に支給されます。この手当は、申請の翌月分から支給されますが、申請手続きがないと、受給資格があっても手当を受けることができません。該当すると思われる方は、早めにお手続きください。
支給対象(受給者)
市内に住所登録があり、高校生年代までの児童を養育している方。
原則として、児童の父母のうち、所得審査の対象となる年の所得の高い方が受給者となります。
毎年6月の所得審査時に、前年の所得が現在の受給者よりも配偶者のほうが高い場合、また、婚姻や離婚などにより生計維持者が変わっている場合は、受給者の変更をする必要があります。詳しくはお問い合わせください。
単身赴任等により児童と別居している場合
受給者となる方が、住民登録をしている市区町村で手続きをしてください。
(注)離婚協議中で別居している場合などは、児童と同居されている方に優先して支給される場合がありますが、状況の確認等が必要となりますので、住民登録をしている市区町村にお問い合わせください。
公務員の場合
受給者となる方が公務員の場合、勤務先からの支給となります。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所のある市町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になったとき
- 退職等により、公務員でなくなったとき
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があるとき(派遣や出向など)
(注)独立行政法人にお勤めの方や公務員でも外部団体等へ派遣されている方は、住民登録をしている市区町村での申請ですが、あらかじめ勤務先に確認してください。
(注)申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
(注)配偶者が公務員で、受給者よりも所得が高くなる場合は、受給者変更が必要です。
対象となる児童
国内に住民登録がある高校生年代までの児童(18歳に到達した後、最初の3月31日までの児童)
(注)国外に居住する児童は、児童手当法に定める留学要件に該当する場合を除き、手当の支給対象とはなりません。
(注)児童福祉施設等に入所(2カ月以内の短期入所や通所を除く)している児童または里親等に委託(2カ月以内の短期委託を除く)されている児童は、手当の支給対象とはなりません。
手当額(月額)
| 対象児童の年齢 |
手当額 |
|---|---|
|
3歳未満 |
15,000円 |
|
3歳誕生月翌月~ |
10,000円 |
「第3子以降」とは、大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している子のうち、3番目以降の児童をいいます。
(例)大学1年生、高校2年生、中学1年生、小学4年生の子を養育している場合
第1子:大学1年生は手当の支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
第2子:高校2年生は支給対象。月額10,000円
第3子:中学1年生は支給対象。月額30,000円
第4子:小学4年生は支給対象。月額30,000円
支給月
- 認定請求等の手続きをした日の属する月の翌月分から支給します。(15日特例を除く。)
- 児童手当は偶数月(10月・12月・2月・4月・6月・8月)の10日(土日祝日の場合は、直前の平日)に各支払月の前月までの2か月分を支給します【定期支給】。
(注)支払通知はありませんので、支給日以降に通帳記入等により入金を確認してください。
(注)申請時期や現況届の提出時期によって、定期支給に間に合わない場合、振込時期が変わることがあります。
| 支給月 | 支給対象月 |
|---|---|
| 10月 | 8月分及び9月分 |
| 12月 | 10月分及び11月分 |
| 2月 | 12月分及び1月分 |
| 4月 | 2月分及び3月分 |
| 6月 | 4月分及び5月分 |
| 8月 | 6月分及び7月分 |
手続きについて
児童手当は、受給資格があっても、申請の手続きがないと受給することができません。事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きをしないと受給できない場合がありますので、ご注意ください。
(注)土曜日.日曜日.祝日・年末年始などの閉庁日を含めて15日を数えます。15日目が閉庁日のときは、翌開庁日までを15日以内とします。
(注)以下の場合以外でも、ご家庭の状況に変更があったときは、期限内に手続きが必要となりますのでご相談ください。
| 手続き種類 | 手続き内容 |
|---|---|
|
出生 |
児童の出生日の翌日から15日以内に認定請求(現在児童手当を受給している方(第2子以降の出生の方)は額改定届)の手続きをしてください。 |
|
転入 |
前の市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きをしてください。 |
|
別居 |
養育している児童と単身赴任等により別居することになった場合は、別居監護申立書等の提出が必要になります。その他の事情で別居する場合は、ご相談ください。 |
手続きに必要なもの
- 請求者本人名義の普通預金の通帳
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)なお、配偶者がいる場合は、配偶者の個人番号が確認できるものも必要です。
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カード等)
- 支給要件児童と別居されている方は、児童の個人番号が確認できるものが必要です。
- 1月1日現在(1月~5月までの間は前年の1月1日現在)日本国外に在住の方は、1月1日が日本国外に在住であることが分かるパスポートの写しが必要です。配偶者の方が日本国外に在住だった場合、配偶者のパスポートの写しも必要です。
- 医療保険の保険者から交付された「健康保険証」、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」のいずれかの写し(請求者が各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)である場合のみ。それ以外の場合は原則不要です。)
(注)健康保険証等の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。
(注)請求者とは、児童を養育する家計の主たる生計維持者になります。父母ともに所得がある場合は、所得が高い方を請求者として請求書を記入してください。
(注)状況によっては、この他にも必要なものがある場合があります。詳しくはお問い合わせください。
現況届
現況届は、毎年6月1日現在の児童の養育状況や年金の加入状況などを報告していただき、引き続き児童手当の支給対象となるかを確認するためのものです。
これまで、すべての受給者に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することにより、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下の場合は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が尾張旭市と異なるとき
- 尾張旭市に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童等)を養育するとき
- 離婚協議中で、配偶者と別居しているとき
- 未成年後見人等、児童手当受給者が父母以外の養育者のとき(施設、里親含む)
- 児童が海外留学をしているとき
- 多子加算の算定対象となり得る大学生年代で進学していない子がいるとき
- その他、状況確認のため、尾張旭市から提出の案内があったとき
(注)現況届の提出が必要な方については、6月上旬に案内を送付します。
以下の変更事項があった場合は、すみやかに窓口へ届け出てください。
- 出生や施設入所をしていた児童の退所など、養育する児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出入を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(転職等をしても、年金の種類が変わらない場合は届出不要)
- 受給者や配偶者が公務員になったとき