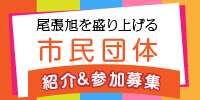本文
国民年金制度の概要
制度の概要
公的年金制度は、老後の暮らし、病気やケガで障がいが残ったときや、一家の働き手が亡くなったときに、経済的な支えとなる社会保障制度の一つで、現役世代が納める保険料が受給世代の給付を支える「世代間の支え合い」の仕組みになっています。
- 加入者
- 任意加入制度について
- 年金がよく分かるマンガ~いっしょに検証!公的年金~<外部リンク>(厚生労働省ホームページへリンク)
加入者
国民年金(基礎年金ともいいます)は以下の3つの種類に分かれます。このうち、第1号被保険者への加入手続きは、市役所で行います。
| 第1号被保険者 | 日本に住む20歳以上60歳未満の自営業、自由業、学生、無職のかたなど。市役所保険医療課で国民年金の加入手続きが必要です。(保険料は本人が納めます。) |
|---|---|
| 第2号被保険者 |
厚生年金に加入している70歳未満のかた。加入手続きは勤務先で行われます。(保険料は勤務先で給料から引かれます。)令和6年10月から短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用が拡大されました。<外部リンク>(日本年金機構ホームページへリンク) |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満のかた。加入手続きは第2号被保険者の勤務先で行われます。(保険料は配偶者が加入している年金制度が負担するため、個人で納める必要はありません。) |
任意加入制度について
一般には日本に住む20歳以上60歳未満のかたは、国民年金の加入が義務付けられていますが、それ以外のかたでも将来受け取る年金額を増やしたり、海外在住期間に死亡したときや病気やけがなどで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金を受給するために任意で加入することができます。加入手続きをした月から国民年金第1号被保険者と同様に毎月保険料を納めます。
任意加入できるかた
60歳以上65歳未満(高齢任意加入)のかた
年金を受けるための受給資格期間が足りないかたや満額の老齢基礎年金に満たないかたは65歳まで加入できます。
65歳以上70歳未満のかた
昭和40年4月1日以前に生まれたかたで、老齢基礎年金の受給資格期間が足りない場合は、70歳になるまでの間、特例で期間を満たすまで加入できます。
海外在住の日本国籍のかた
日本国籍のある20歳以上60歳未満のかたで、国外へ転出するかたは、引き続き国民年金に加入するかしないかを選択できます。詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。国内協力者がいるかたは、海外への住民異動届出の際に市役所保険医療課で手続きをします。