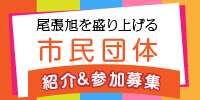本文
生活に困窮している方に対する相談窓口について(生活困窮者自立支援)
「生活困窮者自立支援法」の施行に伴い、尾張旭市では、経済的な理由などで困窮状態となっている方が自立できるよう問題解決に向けた相談窓口を開設しています。
- 電話での相談も可能です。
- 窓口に相談にお越しになられる際はご予約ください。
自立相談支援事業
生活上の様々な問題により困窮状態にあるかたの相談窓口です。相談支援員がお話を伺い、困窮の原因や問題を一緒に整理し、関連機関と連携した支援を行います。
対象者
尾張旭市内に在住で、経済的に生活にお困りの方
(※生活保護を受けている方は対象となりません。)
支援対象者の例
- 仕事がみつからない。
- 求職活動の仕方がわからない。
- 仕事を辞めて家賃の支払いができない。
- 年金と預貯金でひきこもりの子どもを世話してきたが、預貯金がわずかになってきた。など
受付場所
市役所健康福祉部 地域福祉課 生活支援係
受付時間
午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く。)
※年末年始や大型連休などの閉庁日に、住むところや食べる物がなくお困りの方は、市役所代表番号(0561-53-2111)に電話し、状況をお伝えください。
相談から支援までの流れ
Step1お困りごとをお話しください。
地域福祉課で申込後、相談支援員が生活のお困りごとをお聞きします。
Step2一緒に目標をたてましょう。
生活の状況と課題を分析し、どのような支援が必要か一緒に考え、解決に向けた目標を一緒につくりましょう。(プランの策定)
Step3課題解決に向けて、一緒に取り組みましょう。
各種専門機関と連携し、自立した生活に向けて必要なサポートをします。
その他
- 相談は無料です。
- ご本人以外にもご家族からの相談も受け付けます。
- 相談時間が重なった場合、お待ちいただくことがあります。
- ご連絡をいただいた場合でもお待たせすることがありますのでご了承ください。
住居確保給付金
1 受付場所
市役所健康福祉部 地域福祉課 生活支援係
2 受付時間
午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く。)
家賃扶助
離職またはやむを得ない休業等により住居を失ったかたや、または失う恐れのあるかたに、自立のための就職活動が出来るよう、期限を定めて家賃相当額を支給します。(共益費、管理費は支給対象外です。また、支給額に上限があります。)
受給要件
対象者は、次のいずれにも該当するかたです。
1 離職等またはやむを得ない休業等により、経済的に困窮した住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること。
2 次の⑴または⑵に該当する者
⑴ 離職等の場合は、申請日において、離職等の日から2年を経過していない者であること。ただし、この期間中に、疾病、負傷、育児その他福祉事務所長がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは4年)を経過していない者であること。
⑵ やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある者であること。
3 次の⑴または⑵に該当する者
⑴ 離職等の場合は、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
⑵ やむを得ない休業等の場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
4 申請日の属する月における、申請者及びその同一世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(※)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。
※「基準額」=市民税均等割りの非課税となる収入額の12分の1
5 申請日における、申請者及びその同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6倍以下であること。ただし、100万円を超えないものとする。
6 公共職業安定所等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、上記2⑵に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが申請者の自立の促進に なると認められた場合は、申請日の属する月から起算して3月間(支給期間を延長する場合であって、引き続き同取組を行うことが申請者の自立の促進になると認められたときは、6月間)に限り、この取組を行うことをもって、求職活動に代えることができる。
7 地方自治体等が法令または条例に基づき実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者及びその同一世帯に属する者が受けていないこと。
8 申請者及びその同一世帯に属する者のいずれもが暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員でないこと。
関連資料
住居確保給付金(家賃扶助)チラシ [PDFファイル/404KB]
転居費用扶助
同一の世帯に属する者の死亡または本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により、世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者または住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することで家計の改善に向けた支援を行います。(支給額には上限があります。)
受給要件
対象者は、次のいずれにも該当するかたです。
1 申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者若しくはその同一世帯に属する者の離職、休業等により、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること。
2 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
3 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
4 申請日の属する月における、申請者及びその同一世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(※)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。なお、申請者が持家である住宅等に居住している場合は、その居住の維持に要する費用の額を家賃額とし、住居を持たない場合は、居住の確保に要する費用の額を家賃額とする。ただし、生活保護法による住宅扶助基準に基づく額を上限とする。
※「基準額」=市民税均等割りの非課税となる収入額の12分の1
5 申請日における、申請者及びその同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額の6倍以下であること。ただし100万円を超えないものとする。
6 家計の改善のために次の⑴または⑵のいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
⑴ 転居に伴い申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が減少し(申請者が持家である住宅に居住している場合または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
⑵ 転居に伴い申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が増加する(申請者が持家である住宅に居住している場合または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
7 地方自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付を、申請者及びその同一世帯に属する者が受けていないこと。
8 申請者及びその同一世帯に属する者のいずれもが暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員でないこと。
関連資料
住居確保給付金(転居費用扶助)チラシ [PDFファイル/400KB]
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ
生活困窮者自立支援制度<外部リンク>