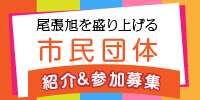本文
男女共同参画関連用語集
| あ行 | |
| あいち女性輝きカンパニー | 女性の活躍促進に向けた取組を積極的に実施する企業等を愛知県が認証するもの。 |
| アウティング | 本人の同意を得ずに、その人の性的指向や性自認などの個人情報やプライバシーを第三者に暴露する行為のこと。 |
| アクション・プラン | 数値目標や具体的な行動指標などを明確化し、実施に移すことを目的とした行動計画のこと。 |
| アライ | LGBTQ+などの性的マイノリティを理解し、支援しようとする人や、その立場を明確にしている人のこと。 |
| アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み) | 自分自身は気付いていない物の見方や捉え方のゆがみや偏りのこと。 |
| M字カーブ | 日本の女性の労働力は、年齢階級別にグラフ化したとき、結婚・出産期に当たる年代に一旦低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するアルファベットのMのような形になること。この背景には、結婚や出産を機に労働市場から退出し、子育てが一段落すると再び労働市場に参入する女性が多いということが考えられる。 |
| LGBT/LGBTQ+ | 女性同性愛者(レズビアン/Lesbian)、男性同性愛者(ゲイ/Gay)、両性愛者(バイセクシュアル/Bisexual)、心と体の性の不一致(トランスジェンダー/Transgender)の頭文字からなる言葉で、性的マイノリティの呼称のひとつ。さらに、自分の性のあり方が分からない、決めていない人(クエスチョニング、クイア/Questioning、Queer)と、多様な性でLGBTQにカテゴライズされない人(プラス/+)を加えた「LGBTQ+」という言葉が使われるようになっている。 |
| えるぼし | 女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出等を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした事業主が、都道府県労働局への申請することにより、を受けることができる厚生労働大臣の認定(えるぼし認定)。 |
| エンパワーメント | 自らの意識と能力を高め、家庭や地域、職場などあらゆる分野で政治的、経済的、社会的、文化的な力をつけること。また、そうした力を持った主体的な存在となり、力を発揮し行動していくこと。(自律性促進、能力開花) |
| か行 | |
| 隠れたカリキュラム | 「校長は男性」「生徒会長は男の子」といった、日常生活のなかで無意識のうちに児童生徒に伝わる行動様式や性別役割などの知識のこと。 |
| カミングアウト | 自分の性的指向や性自認、出自などを他人や社会に打ち明けること。 |
| 固定的性別役割分担 | 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにも関わらず、男性・女性という性別を理由として、役割を固定的に分けること。「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等の固定的な考え方により、男性・女性の役割を決めている例をいう。 |
| さ行 | |
| ジェンダー | 「社会的・文化的に形成された性別」のこと。生まれついての生物学的性別(セックス/sex)ではなく、社会によって作り上げられた社会通念や慣習の中の「男性像」、「女性像」のこと。 例:男は青・女は赤、女はスカート・男はズボン、男は仕事・女は家事 |
| ジェンダーアイデンティティ(性自認) | 自己の性についての認識のこと。自分の性をどのように認識しているか、どのような性のアイデンティティ(性同一性)を自分の感覚として持っているかを示す概念。 |
| 女性活躍推進法 | 働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に役立てる情報の公表を事業主(国や地方公共団体、民間企業等※)に義務づけた法律。 ※常時雇用する労働者が100人以下の民間企業等にあっては努力義務 |
| 女性の活躍促進宣言 | 平成26(2014)年8月に開催された「あいち女性の活躍促進会議」において採択された「あいち女性の活躍促進行動宣言」の趣旨を踏まえ、女性の活躍促進に向けて取り組んでいくことを宣言したもの。賛同する企業等を募集している。 |
| 人権週間 | 毎年12月10日を最終日とする1週間(12月4日から同月10日まで)のこと。この「人権週間」では、人権尊重思想の普及高揚を図る活動が行われている。 |
| 性的指向 | 恋愛や性愛の対象がどのような性別に向かうのかを示す概念。 |
| 性の多様性 | 人によって様々な性のあり方があること。 |
| SOGI(ソジ) | 性的指向(Sexual Orientation)、性自認(GenderIdentity)の頭文字からなる略称。特定の性的指向や性自認の人のみを対象とする表現ではない。 |
| セクシュアル・ハラスメント | 性的ないやがらせのこと。特に雇用の場においては、「職場(労働者が業務を遂行する場所)において行われる性的な言動に対する労働者の対応により、この労働者がその労働条件につき不利益を受けることまたは性的な言動によりこの労働者の就業環境が害されること」とされている。 |
| た行 | |
| 地域包括ケアシステム | 団塊の世代が75歳以上となる令和7(2025)年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制のこと。 |
| デートDV | 交際中の相手から受けるDVのこと。 |
| DV(ドメスティック・バイオレンス) | 配偶者(事実婚、別居を含む)やパートナーなど親密な関係にある(あった)人から振るわれる暴力のこと。暴力には殴る蹴るなどの身体的暴力のみならず、言動で相手を傷つける、外出や交友関係を制限して孤立させるといった精神的な暴力、性行為の強要や避妊に協力しないといった性的暴力、生活費を渡さないといった経済的暴力なども含まれる。 |
| DVの二次被害 | DV被害者を支援する側が、DV被害者の置かれている状況やDV自体に関して理解が不足しているために被害者に対して不適切な対応をとることにより、被害者がさらに被害を受けること。 |
| は行 | |
| 働き方改革実行計画 | 議長を総理とし、労働界と産業界のトップと有識者が参加する「働き方改革実現会議」において、「非正規雇用の処遇改善」「賃金引上げと労働生産性向上」「長時間労働の改める」「柔軟な働き方がしやすい環境整備」など9つの分野について議論し、その成果として平成29(2017)年3月にまとめられた計画。あわせて、その実現に向けたロードマップが示されている。 |
| パワー・ハラスメント | 組織内虐待の1つであり、主に社会的な地位の強いものによる、自らの権力や組織内の優位性を利用したいじめや嫌がらせの事。 |
| ファミリー・フレンドリー企業 | 社員が仕事と生活の調和を図ることができるよう積極的に取り組んでいる企業。 愛知県では、ワーク・ライフ・バランスの実現に取り組む企業を奨励し、その取組を紹介するため、登録制度を設けている。 |
| ファミリーシップ制度 | 互いを人生のパートナーとして尊重し、日常生活において対等な立場で継続的に責任を持って協力する2人が家族であると約した関係であることを市長に対して宣誓し、市が宣誓書受領証等を交付する制度。2人の近親者を含めることもできる。 |
| フレックスタイム制 | 1か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者がその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度のこと。労働者がその生活と業務の調和を図りながら、効率的に働くことができ、労働時間を短縮しようとするもの。 |
| ポジティブ・アクション(積極的改善措置) | 固定的性別役割分担意識や過去の経緯から、営業職に女性はほとんどいない、課長以上の管理職は男性が大半を占めている等の差が男女労働者の間に生じている場合、このような差を解消しようと行う自主的かつ積極的な取組。 |
| ま行 | |
| メディア・リテラシー | メディアからの情報を主体的に読み解き、自己発信する能力のこと。具体的には、メディア内容を主体的かつ客観的に解釈し、選択し、使いこなす能力のこと。また、メディアを使って表現する能力も指す。 |
| や行 | |
| ユニバーサルデザイン | 可能な限りすべての人を対象として想定し、「どこでも、誰でも、自由に、使いやすく」デザインすること。 |
| ら行 | |
| リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康と権利) | 1994年にカイロで開催された国際人口開発会議において提唱された概念。 リプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)は、「人間の生殖システム、その機能と(活動)過程のすべての側面において単に疾病や障害がないだけではなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」とされ、リプロダクティブ・ライツ(性と生殖に関する権利)は、自分の身体のことを自分自身で選択、決定する権利等のこととされている。 中心課題には、いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれ、また、これらに関連して、思春期や更年期における健康上の問題等生涯を通じて性と生殖に関する課題が幅広く議論されている。 |
| 労働施策総合推進法 | 労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上を実現し、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に役立てることを目的とする法律。そのために、経済社会情勢の変化の中で、国が労働施策を総合的に講じ、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者が有する能力を有効に発揮できるようにすることとしている。令和元(2019)年の改正により、職場のパワー・ハラスメント防止のための雇用管理上の措置(相談体制の整備等)について、新たに事業主に義務づけられた。 |
| ロールモデル | 将来像を描いたり、自分のキャリア形成を考える際に参考とする役割モデルのこと。 |
| わ行 | |
| ワーク・ライフ・バランス | 誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、自ら希望するバランスで活動できること。 |