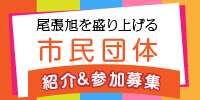本文
介護保険料の概要
介護保険は、社会全体で介護の負担を支え合う制度です。公費と40歳以上の皆さんに納めていただく保険料を財源に制度の運営をしています。
第1号被保険者(65歳以上のかた)の保険料の額
保険料は、前年中の本人の合計所得金額や世帯の課税状況などによって、次のとおり15段階に区分されます。尾張旭市の令和6年度から令和8年度までの介護保険料月額基準額は、5,490円です。
保険料年額の計算方法=月額基準額×保険料率×12月(100円未満切り捨て)
令和6年度から令和8年度の所得段階別保険料額表
| 所得段階 | 対象者 |
保険料率 |
保険料年額 |
|---|---|---|---|
|
第1段階 |
|
0.23 |
15,100円 |
|
第2段階 |
本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円を超え120万円以下のかた |
0.40 |
26,300円 |
|
第3段階 |
本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えるかた |
0.685 |
45,100円 |
|
第4段階 |
本人が市民税非課税(世帯課税)で、合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円以下のかた |
0.90 |
59,200円 |
|
第5段階 |
本人が市民税非課税(世帯課税)で、合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円を超えるかた |
1.00 |
65,800円 |
|
第6段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満のかた |
1.20 |
79,000円 |
|
第7段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた |
1.30 |
85,600円 |
|
第8段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた |
1.50 |
98,800円 |
|
第9段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた |
1.70 |
111,900円 |
|
第10段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた |
1.90 |
125,100円 |
|
第11段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた |
2.10 |
138,300円 |
|
第12段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた |
2.30 |
151,500円 |
| 第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上800万円未満のかた | 2.40 | 158,100円 |
| 第14段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満のかた | 2.50 | 164,700円 |
|
第15段階 |
本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上のかた |
2.60 |
171,200円 |
第1段階、第2段階及び第3段階の保険料は、公費による軽減措置後の金額です。
「課税年金収入額」とは
税法上課税対象の収入とされる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入をいい、非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません。
「合計所得金額」とは
1事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
2総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
1と2の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額。ただし、繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額。
なお、平成30年度から保険料の算出に使われる合計所得金額は、短期・長期譲渡所得に係る特別控除の金額を差し引いた額となります。
第1段階から第5段階の合計所得金額は年金収入に係る合計所得金額を差し引いた額となります。
介護保険料の徴収方法
介護保険料の徴収方法には、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。
特別徴収(年金天引き)
年金の定期払い(偶数月年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。特別徴収となるかたは、年額18万円以上の老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金を受給しているかたです。
普通徴収(納付書納付)
口座振替または納付書により、年8回の納期(年度途中に転入、65歳到達した年度は年8回より少なくなります。)で介護保険料を納めていただきます。特別徴収の対象とならないかたは、すべて普通徴収となります。
納付書で納付していただくかた(普通徴収のかた)
- 老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金の額がいずれも年額18万円未満のかた
- 老齢福祉年金または恩給のみ受給しているかた
- 新たに65歳になられたかたや新たに尾張旭市に転入されたかた
- 年度の途中で所得額の変更があったかた
- 保険料を天引きしている年金が一時差止めになったかた
(これらの場合以外でも、納付書を送付する場合があります。)
普通徴収のかたの納付方法
普通徴収のかたの納付の方法については、介護保険料(普通徴収)の納付についてをご覧ください。
介護保険料の徴収猶予・減免について
災害により損害を受けた場合や生計中心者の死亡、失業等により収入が著しく減少した場合などは、保険料の徴収猶予や減免を受けることができます。申請方法については、介護保険料の徴収猶予・減免をご覧ください。
介護保険料の納付額
毎年1月1日から12月31日の間に普通徴収により納付した保険料の納付確認書を、翌年の1月下旬に送付します。なお、特別徴収で納めているかたは、日本年金機構などから届く源泉徴収票で、介護保険料額を確認してください。
その他
40歳から64歳までの第2号被保険者の介護保険料については、各医療保険者を通じて徴収されますので、詳細は、加入している各医療保険者にご確認ください。