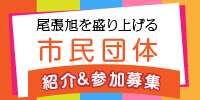本文
思春期子育て講座
趣旨
心や身体の発達とともに不安定になりやすい思春期の子どもたちを取り巻くさまざまな問題を、彼らに接する大人として、いろんな角度から、専門の先生をお招きしてお話を伺いながら、子どもたちを支えていくための方策を考え、工夫し、日々の対応に活かせるヒントを掴んでいただく助けとなるよう、思春期子育て講座を開催しています。
受講方法
講師や内容によって受講形態が変わります。中央公民館や各家庭でご参加いただくことができます。
● 対面受講
● 対面、及びオンライン併用受講
● オンライン受講
思春期子育て講座(後期)を募集します
1 時 間 : いずれも午前10時から午前11時30分の90分程度
2 受講方法 : 中央公民館での対面受講か、自宅でのZoom受講(第3回は対面受講のみ)
| 第1回 |
10月23日 木曜日 |
「私の青春時代、そして母になって思うこと」 椙山女学園大学 教授 堀田 あけみ さん 愛知県立中村高等学校在学中の1981年に『1980アイコ十六歳』が文藝賞を受賞し、最年少での受賞として話題を呼ぶとともに、映画化・コミック化もされました。そんな半生を振り返りながら、自身の思春期について、そして子育てについて語っていただきます。 |
| 第2回 |
11月11日 火曜日 |
「ネットいじめにどう向き合うか」 愛知教育大学 准教授 黒川 雅幸 さん 近年、SNSを使った誹謗中傷や嫌がらせを受けるケースが増えて来ています。子どもたちの間で起きている、大人からは見えにくいネットいじめ等の実態や、それに向き合うために何が必要かをお話していただきます。 |
| 第3回 |
11月27日 木曜日 |
「豊かな人間関係を築くための対人コミュニケーションとは?」 愛知淑徳大学 教授 小川 一美 さん コミュニケーション力とはどのようなものか。そして、それを育成するにはどのような働きかけが効果的かを研究結果に基づいてお話していただきます。 |
令和7年度思春期子育て講座(後期)チラシ [PDFファイル/4.1MB]
申込フォーム<外部リンク>または電話か窓口で直接お申込ください
申込期間 : 9月12日(金曜日)~10月8日(水曜日)
電話の場合 : 0561-76-8181 (平日午前8時30分から午後5時15分まで)
これまでの講座
講座の講師とテーマ
| *第1回 中部大学 准教授 渡邉 素子 さん |
| 「思春期の子どもの心の深層」 |
| *第2回 NPO法人アスクネット 森澤 ゆかり さん |
| 「今、社会で求められる人材とは?」 |
| *第3回 椙山女学園大学 准教授 奥川 ゆかり さん |
| 「子どもたちに伝えたい命と性」 |
| *第4回 中京大学 教授 中野 貴博 さん |
| 「子どもの体力の現状および運動を通した子どもの育み」 |
| *第1回 公立小中高スクールカウンセラー 山口 力 さん |
| 「本物の自信を育む子育て -揺れ動く思春期の心ー」 |
| *第2回 愛知東邦大学 准教授 吉村 道孝 さん |
| 「睡眠・生活リズムを整えることの重要性」 |
|
*第3回 愛知県尾張福祉相談センター 児童専門監 吉川 徹 さん |
|
「家庭でのゲーム、ネット利用のルール作り -なぜゲーム、ネットの世界から離れられな いのかー」 |
| *第4回 尾張旭市心のアドバイザー 西村 則子 さん |
| 「子どもの人生、自分自身の生き方、家族のあり方を考える」 |
| *第1回 漫画家 棚園 正一 さん |
| 「不登校の時間が教えてくれたこと」 |
| *第2回 岩倉市人権擁護委員・元中学校教諭 鵜飼 洋子 さん |
| 「私の歩みから子育てを考える」 |
| *第3回 町のお母さん保健室Hidamaly代表 澤田 有心子(ゆみこ) さん |
| 「自己肯定感を育てる子育て」 |
| *第4回 キャリアコンサルタント 柴田 朋子 さん |
| 「子どもの自立のために親がすること、してはいけないこと」 |
過去の講座の紹介
令和6年度後期講座、「家庭でのゲーム、ネット利用のルール作り -なぜゲーム、ネットの世界から離れられないのかー」(吉川 徹 さん(愛知県尾張福祉相談センター 児童専門監)の講義の一部を視聴していただけます。(令和7年6月30日まで)
参加者の声
- 先生の「思春期の子どもに対して、または自分に対してイライラするのは当たり前」との言葉で、少し肩の力が抜けた気がします。最近、子どもを褒めることができていませんでしたが、小さなことから目を向けてみようと思います。
- 反抗期と聞くとネガティブなイメージになるが、子どもが自分の意見を主張する訓練をしている、ということを念頭において接していきたいと思いました。
- 子どもたちが没頭していることが、親にとっては心配なことでも、見方を変えて一緒に話をして相談しながら、見守って応援していけたらいいなと思いました。
- 子どもたちを信頼すること、目を掛け手を掛けないということの大切さを学びました。大人が子どもの手本となるよう心掛けたいなと思いました。