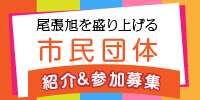本文
避難行動要支援者に対する援助
避難行動要支援者とは
要配慮者について
要配慮者とは、災害が起きたとき、自分だけでは自分の命を守るための行動をとることが難しいかたをいいます。
- 高齢者
- 障がい者
- 乳幼児及び妊産婦
- 外国籍の方
- 傷病者
などが要配慮者とされており、災害が発生した場合、情報把握、避難、生活の確保などの活動を、的確かつ迅速に行いにくい立場に置かれてしまいます。
避難行動要支援者について
要配慮者の中でも、災害時に一人で避難することが困難なかたを「避難行動要支援者」といい、避難行動要支援者を支援するには、一人ひとりの状況やハンディを理解して支援方法を考えることが必要です。
避難行動要支援者のためにできること
災害時は地域での助け合いがとても大切です、普段から声を掛け合い、交流して関係を築いておきましょう。
平常時
個別支援プランの作成
事前に避難行動要支援者一人ひとりに合わせた支援プランを作成することが、災害発生時の的確な支援につながります。
実際に支援する人を決めておくことをはじめ、かかりつけの病院や特に配慮が必要なことなどを把握し、まとめておくことで、災害発生時に支援をスムーズに行えるようにします。
避難行動要支援者支援事業について
市では個別支援プランを作成する町内会に、「地域防災活動補助金」を交付しています。
詳細は「地域防災活動補助金の概要」のページをご確認いただくか、市危機管理課に直接お問い合わせください。
災害発生時
要配慮者は、災害が起こった時に危険に気がついていないことや、安全に避難するための行動をとることが難しい場合があります。ご自身が避難される際に余裕があれば、要配慮者ご本人やそのご家族に声をかけ、どんな支援が必要かを確認し、一緒に避難しましょう。
支援の例
高齢者・傷病者
援助が必要なときは、複数の人で対応する。
急を要するときは、ひもなどで背負い安全な場所まで避難する。
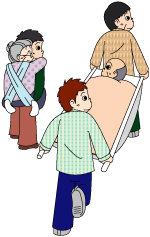
肢体の不自由な人
車いすは、階段では必ず2人以上、できれば3~4人で援助する。
上がるときは前向きに、下がるときは後ろ向きにして恐怖感を与えないように。
とっさの脱出、避難の際に要支援者1人に対して、支援者が2人以上いるとは限らない。ひもなどで背負い、支援者の両手は自由がきくようにする。
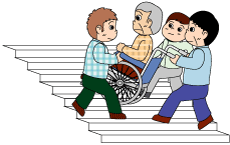
耳が不自由な人
話をするときはまっすぐ顔を向け、口はなるべく大きく動かして話す。
筆談(筆記法)は手のひらに指先で文字を書くやり方でもよい。
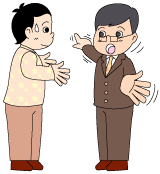
目の不自由な人
杖や杖を持った手をひっぱったり、後ろから押したりしない。
半歩前に立ち、ひじの上を軽く持ってもらい、ゆっくり歩く。
方向や目の前の障害物の位置などは、時計の文字盤の位置を想定して伝える。
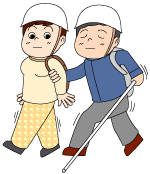
外国人・旅行者
とっさのときは、身振り手振りや、やさしい日本語で話しかけ、孤立させないようにする。
旅先では非常口の確認を。
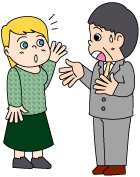
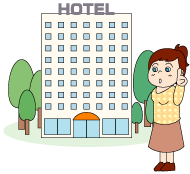
出典
「愛知県防災・減災お役立ちガイド」