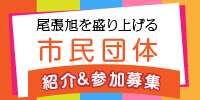本文
市長コラム「足下に泉あり!」2024年

広報おわりあさひにて連載している市長のコラム「足下に泉あり!」を、ホームページでも紹介します!
バックナンバー
- うちの子(令和6年12月号 Vol.20)
- 女性活躍の先にあるもの(令和6年11月号 vol.19)
- 渋沢好きの日本人(令和6年10月号 vol.18)
- 若きボランティア(令和6年9月号 vol.17)
- 古巣はありがたや(令和6年8月号 vol.16)
- プロフェッショナル(令和6年7月号 vol.15)
- 「平安」の価値(令和6年6月号 vol.14)
- 新たな船出にあたり(令和6年5月号 vol.13)
- 小学生との出会い(令和6年3月15日号 vol.12)
- 健気な足かせ(令和6年2月15日号 vol.11)
- 所変われば健康も・・(令和6年1月15日号 vol.10)
掲載内容
うちの子(令和6年12月 vol.20)
5月号からリニューアルした「広報おわりあさひ」、いかがでしょう。私が受けた一番の反応は、コラムから「チェルシー」を抱えた写真が消えたことです。愛犬家の皆さまにご心配? をお掛けしたようですが、誕生20周年の「あさぴー」と一緒に散歩しているイラストに変身しています。
さて、年配のかたが「うちの子は天才」と言えば、それはヒトではなく、ペットのことを指す、昨今ではごく普通の表現となりました。そこで、ワンコの話題を一つ。
5月に厚労省が発表した調査では、認知症患者数は、16年後の令和22年には584万人となり、高齢者の6.7人に1人が該当します。ただ、光明もあります。9年前の推計は802万人でしたから、大幅に下回る結果になりました。認知症と「軽度認知障害」の合計数はほぼ同じなので、健康意識の高まりによって、認知症から予備軍へシフトしたと思われます。
ここで、ワンコが華々しく登場。昨年10月、東京都健康長寿医療センターが、犬を飼っている人は飼っていない人に比べ、認知症リスクが何と40%低くなると発表しました。
強い共感力=癒やしパワーに加え、犬特有の散歩を介した運動や知人の輪(犬友)の広がりも、猫に比べて大きな効果に結びついたようです。ワンコ、凄いですね。どんな薬よりも、圧倒的です。全ての愛犬家の願いは、「うちの子」が幸福であること。私もですが、高齢者がワンコを飼うには、愛犬の最期を看取る責任と覚悟が必要です。自身の健康寿命と犬の寿命を考慮せざるを得ません。一つの方法ですが、高齢者がワンコを新たに飼うことを是とするためには、大人の保護犬を選ぶこともアリと思います。健康都市宣言20周年の節目の年にあたり、私からの提案でした。

女性活躍の先にあるもの(令和6年11月 vol.19)
市役所での女性活躍を後押しするため、8月19日に、愛知県副知事の牧野利香さんをお招きし、講演会を実施しました。
副知事は、平成6年に労働省に入省、内閣府の男女共同参画局、厚生労働省の政策統括官付参事官を経て、令和5年の愛知県着任後は女性活躍・県民文化・福祉・保健医療・環境などを担当されています。
講演のテーマは、「女性が輝く社会をめざして」。職員63人が参加し、うち女性は39人で、関心の高さを物語っています。
私が副知事に講演をお願いした切っ掛けは、多くの女性職員が、積極的な昇進を望んでいないと知ったからです。これは、民間企業でも大変深刻な問題で、女性の幹部登用が進まない大きな原因でもあります。そこで、ご家庭と自身のキャリアを両立されている副知事の存在そのものが、職員への刺激になると考え、無理を言って時間を作っていただきました。
女性職員へのメッセージの部分を紹介します。
1.「仕事か、子育てか」ではなく、「仕事も、子育ても」。将来、組織を担う立場になることを見据え、子育てをしながら多様な仕事を
体験することが重要
2.自分一人で完璧を目指さず、他人を巻き込むこと
3.「管理職」はチャレンジ精神で、まずはやってみる
4.ワークライフバランスがとれた職場への改革。職場慣行・仕事自体の見直しと同時に、部下を育てることに注力する
さてさて、11月は、人事課への自己申告提出の季節です。男女ともに職員の皆さんのチャレンジ精神が、どういう形で表れるのか、楽しみです。
女性活躍の先には、S D G s の5 番目の目標「ジェンダー平等」の社会が待っています。誰もが存分に活躍できる組織を目指し、職員のやる気を精一杯応援したいと思います。
渋沢好きの日本人(令和6年10月号 vol.18)
7月3日より発行されている新紙幣を最近よく見かけるようになりました。ご存じ、新1万円札の顔は、「近代日本経済の父」渋沢栄一です。
書店では、NHK大河ドラマ以来の渋沢特集コーナーが設けられています。日本人、特に会社勤めの人は渋沢栄一が大好きで、故にさまざまな関連本が出版されています。
どこの本屋さんでも一押しは、『現代語訳 論語と算盤(そろばん)』(守屋淳/訳 ちくま新書/出版)です。注目すべきはタイトルで、論語「と」算盤であって、論語「か」算盤ではありません。
私たちはこの本を読むと、どこかで見たような、聞いたような感覚を抱きます。渋沢は明治の黎明(れいめい)期に約500社の会社、500以上の社会事業に関わり、結果、歴史ある名だたる企業が、彼の思想を自社の社訓などに取り入れました。
論語(=道徳)と算盤(=金もうけ)を両立する「利他の精神」は日本企業に広く浸透し、その企業理念に「社会やお客様と共に」といった文言を採用しています。世界に冠たる日本株式会社の強さは、渋沢経営哲学の延長線上にあると言え、昨今、世間を騒がすガバナンスやらコンプライアンスの問題も、突き詰めれば、彼が主張する「道義の伴った利益の追求」の成否次第となります。これだけの偉業を成し遂げるストレスの中、昭和初頭91歳の長寿であったことも驚きです。
最後に、渋沢の人生訓「夢七訓(ゆめしちくん)」を紹介します。「夢なき者は理想なし 理想なき者は信念なし 信念なき者は計画なし 計画なき者は実行なし 実行なき者は成果なし 成果なき者は幸福なし ゆえに幸福を求むる者は夢なかるべからず」。
幸福を得たければ、まず夢を持つべし。深いですね。新札をまずは拝んでから、使いたいと思います。

若きボランティア(令和6年9月号 vol.17)
5月25日、旭中学校の体育館で、「第6回 ごちゃまぜ運動会」が、170人を超える参加者のもと、開催されました。
この運動会は、障がいの有無、年齢・国籍・性別など関係無く、誰もが気軽に集まって、楽しみながら障がい体験ができる、非常にユニークなイベントです。
第1回は、本市出身の押富俊恵さん(昭和56年生まれ、令和3年逝去)が創設したNPO法人ピース・トレランスによって、平成29年に開催されました。作業療法士であった押富さんは平成18年に重症筋無力症となり、25歳で人工呼吸器を装着、28歳からはほぼ寝たきりの生活を余儀なくされます。病と闘いながら、車椅子に酸素ボンベを積んで社会福祉活動に尽力し、常に前向きに生き抜かれた押富さんの熱情には圧倒されます。
亡くなられた後も運動会の存続を願う声は多く、令和4年からは市が主催して、先のNPOへ運営委託する体制となり、今に至ります。
さて当日、驚いたことに、96人のボランティア中、学生さんは、名古屋経営短期大学、名古屋柳城女子大学、名古屋産業大学、中京大学、日本福祉大学、椙山女学園大学、東海学園大学、瀬戸北総合高校、杏和高校から総勢85人。
玉入れや車椅子綱引き、ボッチャなど多くの競技が行われる中、障がいのあるかたたちをサポートし、 楽しんでもらおうと頑張る、もてなしの姿に触れ、感動しました。
人間関係の在り様が大きく変化する昨今、学生さんたちの「社会貢献」への高い志は、地域コミュニティを守る一筋の光のように見えます。若い力に期待です。

古巣はありがたや(令和6年8月号 vol.16)
4月18日、名古屋鉄道(株)との間で、地域活性化包括連携協定を締結しました。内容は、同社の関連会社も含めた連携とし、まちづくりやにぎわい創出など、おおよそ思いつくもの全てを網羅できるよう多岐にわたります。
同社では、春から「瀬戸線沿線価値向上プロジェク ト」が始動し、ハイキングなどのイベントは既に実績がありますし、ふるさと納税のコラボ企画も検討しています。また旅行会社には早速6月から、おいしい紅茶のお店を組み込んだ着地型観光商品を販売してもらっています。その他、バスやタクシ一会社とは、社会実証実験の打ち合わせを重ねています。具体化の発表を、楽しみにお待ちください。
さて、同社の副社長であった自身のキャリアを思う と、この日は個人的にも感慨深く、市長就任1年の集大成とも捉えています。それにしても不思議な縁、運命の巡り合わせを感じます。
当日は、副社長の鈴木清美氏が社長の代理で来庁してくれました。彼には鉄道事業本部長の前職時も、三郷駅周辺まちづくり事業でお世話になっていました。4月からは「代表取締役副社長執行役員 地域活性化推進本部長」と、少々長い役職に就かれての初の大仕事?となり、今後は本市のカウンターパートとなってもらえます。大変、うれしく光栄に思っています。 昨年来、こうした協定は中日ドラゴンズを皮切りに、多くの企業・団体・大学と積極的に締結を行ってまいりました。
まずは、矢継ぎ早に種まきをしたということです。 すぐに芽が出て、茎が伸び、葉が茂り、花が咲きます。 うまく育てば、立派な実がなるはず。市民の皆さまと一緒に、大きな果実を収穫できることを願っています。きっと、おいしいですよ。
プロフェッショナル(令和6年7月号 vol.15)
3月30日、城山公園で開催した「さくらまつり」会場で、本市初のふるさと大使である、DA PUMPの TOMOさんのお披露目式をとり行いました。記念ダンスイベントは、何と500人の観客で盛り上がり、参加したダンス教室選抜の子どもたちは大感激です。
彼とは、昨年3月の「旭色プロジェクト」で、私と一緒に食レポをして以来のご縁ですが、初対面でも、ふるさと・尾張旭愛を熱く語る、本当に気さくで礼儀正しい好青年です。
私は、シティプロモーションに本格的に取り組みたいと考え、その一環として「尾張旭市ふるさと大使」の制度を創設し、その第1号に、三郷小・東中出身のTOMOさんに、彼の誕生日の2月2日付けで就任していただきました。今後は、本市の魅力発信、まちのにぎわい創出への力添えを期待しています。
例えば、本市をイメージした創作ダンスで、子どもたちと一緒に街中で踊ってもらうなどなど・・・、夢は 広がります。
昨年10月の「小中高生ダンスフェスティバル」、そして「さくらまつり」、5月に開催された全国植樹祭5周年記念「AICHI GREEN FES」、これら一連のイベントで気付くことは、平凡な表現ですが、「プロのオーラ」、まさに魔法ですね。
ダンスに夢中の子どもたちにとって、彼は努力をしてプロになった憧れ、神様的存在であり、その一挙手一投足をキラキラした目で見つめ、発する言葉の奥にある意味を懸命に読み取ろうと頑張ります。
これは、私たち普通人には残念ながら望むべくもない、 プロと呼ばれる人のみが持 つパワーなのです。感服しきりです。

「平安」の価値(令和6年6月号 vol.14)
今年のNHK大河ドラマは、紫式部が主人公です。 ご存じ、世界最古かつ最高峰の長編小説『源氏物語』の作者であり、平安京を舞台に活躍した人物です。そして、「平安」と名付けられた都の名からは、安らかで無事平穏を願う、時の為政者の強烈な祈りを感じ取ることができます。
令和6年能登半島地震に関し、本市は、輪島市と災害協定を結んでいるご縁から、独自の支援を続けています。その一環として、市内外から多額の募金がかない、3月27日に輪島市長に目録の形で支援金を直接お渡しできました。繰り返し述べられた「感謝」という言葉を、善意をお寄せいただいた市民・企業・団体の 皆さまにお伝えいたします。誠にありがとうございま した。引き続き、寄付をはじめとする支援活動に取り 組んでまいります。
私は平成23年6月に、名古屋鉄道の取締役総務部長に就任しました。東日本大震災が、その3カ月余り前に発生した年です。私の最初のミッションは、偶然にもBCP(事業継続計画)策定で、震災が社内に危機感をもたらしたことが背中を押し、個人的にも使命感を強く覚えました。
現在も、名鉄グループの総合災害対策訓練は、このBCPに沿って、年一回実施されています。当時、訓練レベルを飛躍的に向上させた自負はありましたが、万一のとき、本当にうまく運用できるのか、不安は常に付きまとっていました。
こうした経験を踏まえ、市長としての重要施策の一丁目一番地に「安全安心」を掲げています。市民の暮らしを守るため、本市の安寧を祈りつつ、かけがえのない 「平安」な時にこそ、可能な限りの最適最善の備えに努めてまいります。

新たな船出にあたり(令和6年5月号 vol.13)
4月に新入学や入社などの人生の節目を迎えられた多くのかたがたに、新たな世界での活躍を願い、 エールを送ります。
希望に満ちて、やる気いっぱいの人は、今月のコラムは読んでいただく必要はありません。不安やプレッシャーを感じている人には、少しだけですがお役に立 つかもしれません。
詩を紹介します。随分と昔、誰の作かも知らないままに、冒頭部分を何かの折に読んで心に残っていたのですが、先般、ロシア文学者のかたが、某新聞のコ ラムで全文を引用されていました。
泣くな 悩むな/過去など ない!/愛想よく にぎやか に/光が 飛び込んでくる/眠るとき 君は死に/朝 起きて よみがえる/無心で見よ 空の彼方を/永遠 に続くは 望むもの/つらい思いは 失せる/絶えず 進めよ/前へ 前へと/
ワレーリー・ブリューソフ
死ぬほど爆睡して、翌朝には復活。何か、晴れ晴れとした気分になりませんか。鬱々とする暇があればまずは全力投球、元気付けられますね。
彼はロシアの詩人ですが、禅の修行にも、夜、すわると書いて「夜坐」というものがあり、心を静めてから眠りにつくことが決まりとなっているそうです。 私のルーティンは、毎晩のお風呂の中で、一日を振り返り、少なくとも翌日の必要な行動はシミュ レーションして決めてしまいます。
頭の整理さえ済めば、安心して即、眠りにつくことができます。 一度、お試しください。
小学生との出会い(令和6年3月15日号 vol.12)
昨年末、某新聞社から「今年(令和5年)の漢字」を問われ、頭に浮かんだのは「会」。コロナ禍も落ち着く中で、多くの「出会い」がありました。「会」は、出会いの会です。
今年になり、小学生たちとの新たな出会いが続きました。まずは、市長ふれあい訪問事業の一環で1月25日に実施した「市長、小学校に行く! 」です。城山小学校の6年生全員が、自然・食べ物・生活・建物のテーマでグループ討論し、私に質問・提案をしてくれました。本市の短所・長所の洗い出しは鋭く、何とか回答したのですが、児童たちの満足度が気になるところです。※
まとめとして、6年生は中学生となる不安な気持ちも持っているはずと思い、「ゆっくりと自分のペースで歩んでほしい。何度でもやり直せる長い時間が誰にも平等にある。みんなの未来には無限の可能性がある」と伝え、授業を終えました。
次いで2月2日、トンガ王国のT ・スカ・マンギシ全権駐日大使が、 渋川小学校を訪問してくださいました。同国とは、2005年日本国際博覧会(愛知万博)の一市町村 一国フレンドシップ事業でのご縁があります。令和4年の同国沖の海底火山噴火の際に、渋川小学校児童が独自で行った募金を、当時の4年生の励ましの寄せ書きと共に贈ったことで、現在6年生となった児童たちに感謝を伝えたいと、大使が望まれて実現しました。
児童たちは、東日本大震災の体験から生まれた歌「群青」を合唱するなど、大使との交流を楽しみました。私が昨年3月に大使館を訪問して以来の念願でしたが、卒業前に何とか叶えることができました。
市長就任2年目に入り、本年はどんな「出会い」が続くのか、楽しい良き出会いを期待しています。
※後日「自分の住む市のことを学べてよかった」 など、児童全員の感想を聞くことができました。 今後、他の小学校も訪れたいと考えています。
健気な足かせ(令和6年2月15日号 vol.11)
昨年11月、本地ヶ原保育園に職員休憩室が完成しました。
これは、尾張旭ライオンズクラブ (LC)様からの現物寄付で設置することができたものです。会員の皆さまに、改めて深く感謝申し上げます。
この発端は、昨年3月上旬、保育園を順に視察していた時、市内 で唯一、同園には保育士用の休憩室が無いことを知ったことです。体調不良の際は、遊戯室の片隅を囲って横になる、また、スペース不足から廊下で食事を取ることもあるなどなど。精神的・体力的にもストレスが大きく、職員間の人間関係にも影響する悩みを、園長先生からお聞きしました。
保育士の離職率が高く、結果として要員不足から、さらに一人の負担が大きくなるといった厳しい状態でした。
そうした折にLC様から寄付の打診があり、正に天の恵みだと思い検討しました。市職員には、皆さんの想像される以上の驚きをもって受け止められました。
役所の人間は生真面目で、自分たちのことは後回しという美徳、ある意味、健気な思い込みがあります。
今回の寄付の使い道は、これまで誰も思いつかなかった役所の常識をひっくり返す画期的なものです。私は、せっかくの浄財であればこそ、緊急性と重要性に鑑みて、前例にとらわれることなく有意義に使わせていただくことが、ご厚意に報いる最善の道だと考えます。
職員の職場環境の改善は、保育現場はもとより行政サービス の向上に直結するのですから、 硬直した発想からは脱却するべきなのです。これも、大きな改革の一つではないでしょうか。
所変われば健康も・・(令和6年1月15日号 vol.10)
新年を迎え、誰もが関心のある「健康」について考えてみたいと思います。
ご存じのとおり、本市は平成16年に世界保健機関(WHO) の理念に賛同し、健康都市連合の設立メンバーとして加盟が承認され、健康都市宣言を行いました。翌17年には日本支部が設立され、本市は「尾張旭市健康都市プログラム」を策定し、以来、人もまちも元気にするためのさまざまな施策に取り組んできました。
そして昨年11月、ヨーロッパ の健康都市市長団の視察を受け入れました。午前中は名古屋市内で、WHO欧州地域事務局のほか、フィンランドやギリシャなど6カ国の市長さんらに尾張旭の取り組みをプレゼンテーションし、午後には全員、バスでスカイワードあさひに移動、あいにくの雨で城山公園の視察は断念しましたが、展望室や歴史民族フロアを熱心に見ていただきました。
先方のプレゼンで興味深かったのは、フランスのレンヌ市の発表です。日本の健康都市では、 大半の取り組みが健康寿命を延ばすなど、高齢者向けなのですが、フランスでは国を挙げて 「超加工食品(いわゆるジャンク フード? )」の追放に取り組んでいるそうです。
対象を高齢者に絞り込むのではなく、子どもなど若年世代からの底上げで、広く国民全体の健康を守ろうとする取り組みで、彼らの感性が「健康=長寿」と捉える日本とは大きく異なっていることに、ハタと気付いたわけです。
健康についても、固定観念・先入観というものはあるのですね。心と体の調和、愛情、食育、医療、 教養、スポーツ・運動、文化・芸 術、芸能・趣味などなど、健康への道筋は奥深く多様なのです。


関連リンク