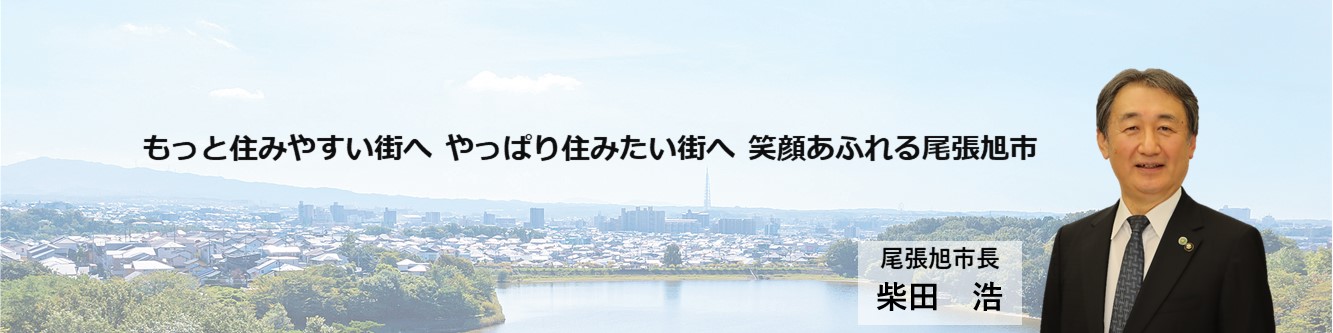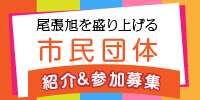本文
施政方針
令和8年度施政方針(全文)
令和8年第2回尾張旭市議会定例会の開会にあたり、令和8年度における市政運営に関する私の方針と、重点施策の概要を申し述べます。
はじめに
私が市長に就任し、早やこの2月で4年目に突入いたしました。「突入」という表現が適切かどうか迷いますが、気持ちとしては「突入」以外に思いつきません。この間、所信表明で掲げたスローガン「市政の安定とさらなる発展を!」を胸に、常にスピード感を意識して、まちづくりに邁進してまいりました。
私が、当初から注力してきた施策は、防災をはじめとする「安全安心」のまちづくりです。「安全安心」は、市民生活を支える重要な基盤であり、一丁目一番地の施策と位置付けてきました。特に、中央防災倉庫が完成することで、本市の防災体制は格段に強化され、災害時に想定される市民の生活環境の大幅な改善が期待できます。
また、「子育て・教育」の充実にも、注力してまいりました。少子・超高齢社会が進展する中で、とりわけ若い世代の方に、本市に「住みたい」「住み続けたい」と感じていただけるまちづくりは、本市の将来を左右する極めて重要な視点です。本年4月には、民間保育園2園が開園します。これにより、待機児童ゼロを達成し、今後も維持を図ることで、子育てに優しいまちづくり、子どもたちが健やかに成長できる環境づくりに努めます。
さて、私事ですが、1年ほど前に癌の手術を受け、合併症の併発により、2か月間の長期入院を余儀なくされました。その経験から、改めて、楽しく健康に暮らすことの大切さを実感いたしました。大病を経験した健康都市の首長として、最も基本的なセーフティネットである、健康・福祉施策のさらなる充実に取り組んでまいりたいと考えています。
これらを踏まえ、令和8年度の市政のテーマを、「楽しく健やかな暮らし」といたします。市民の暮らしに「楽しさ」という彩りを加える取組として、市民プールが生まれ変わり、本年の夏には「スイっとあさぴー」としてオープンします。また、秋に実施する市民祭を、他の祭りと統合して、より魅力ある形で開催いたします。
このほか、多くの市民の皆さまから要望をいただいている中日ドラゴンズのファーム拠点の誘致については、諸条件を確認しつつ、前向きに検討を進めてまいります。来週3月5日には、WBCが開幕し、本市出身の高橋宏斗投手の活躍が期待されますし、9・10月にはアジア・アジアパラ競技大会の開催もあり、本市でも聖火リレーが行われ、楽しみは満載です。
(高橋宏斗投手の「高」の字は、(はしごだか)が正しい漢字となります。)
次に、三郷駅周辺まちづくり事業は、今後、目に見える形で進展してまいります。昨今の資材費・人件費高騰、深刻な労働力不足の中、当然、不安に思われている市民の方もおいでになるとは思いますが、何もしなければ、まちは急激に老化し、ゆるやかに縮小していきます。本市の中核である三郷駅周辺に賑わいを生み出し、人々が集い、まちの活力を創造していくことは、本市の未来のため、後世にバトンを渡すために、今こそやるべき重要な投資です。本市の新たなシンボルとして、魅力的な駅前拠点となるよう、着実に事業を進めてまいります。
また、令和8年度は、水道料金・下水道使用料の改定や、公共施設使用料の見直しなど、市民の皆さまに追加のご負担をお願いすることとなります。社会インフラや公共施設を、今後も安全安心にご利用いただくために、必要な対応であることをご理解いただければ幸いです。
限りある財源を最大限に活用し、事業の優先度を見極めながら、第六次総合計画に謳う、めざすまちの未来像「幸せつむぐ 笑顔あふれる 尾張旭」の実現に向け、引き続き、全力で市政運営に取り組んでまいります。
令和8年度における重点施策の概要
それでは、令和8年度における、重点施策の概要について、申し上げます。
重点施策1「安全安心」
はじめに、重点施策の1項目め、「安全安心」についてです。
防災に関しては、中央防災倉庫がまもなく完成し、この夏には運用が始まります。能登半島地震の被災地への職員派遣などで、実際に現地で支援に携わった職員の声を活かしながら、資機材整備や計画、訓練を見直し、防災体制の更なる強化を図ってまいります。なお、避難所の環境改善として、トイレカーの配備を予定しています。
災害時の指定避難所である公民館や東部市民センターについては、トイレの洋式化工事が完了し、3中学校の体育館と柔剣道場には、空調設備を設置しました。ハード面での防災体制は、随分と整ってきたと考えています。
また、水道施設では、令和7年度に幹線水道管耐震化基本計画の見直しを行い、管路の整備方針と年次計画の検討を済ませました。これを受け、引き続き、水道管の耐震化を計画的に進めてまいります。
次に、消防・救急体制については、消防庁舎の環境改善を図るため、待機室の空調や浴室の改修を実施します。また、救助工作車を更新して、消防力の強化を図ります。
交通安全対策では、令和7年度から実施している、庄中南地区での「暮らしのみち整備工事」を、引き続き進めるほか、労災病院西交差点の改良工事により、渋滞緩和や安全性・利便性の向上に取り組みます。
重点施策2「健康・福祉」
次に、重点施策の2項目め、「健康・福祉」についてです。
まず、「健康」に関しては、健康都市事業を、引き続き推進してまいります。そして、妊婦へのRSウイルスワクチンの定期接種化や、小学校入学前の子どもの心身の発達をサポートする5歳児健康診査の開始など、新たな取組も充実させます。
また、全国的に公立病院が厳しい経営状況にある中、この地域の医療を支える公立陶生病院の支援に、組合構成市として注力します。
国民健康保険については、保険税率の急激な上昇の緩和を図るため、一般会計からの財政支援を行い、被保険者の経済的負担を軽減します。
これら従来からの重要な健康施策に関しては、維持・継続を図ることで、市民の皆さまの健やかな暮らしを守ってまいります。
次に、「福祉」に関しては、本地原と瑞鳳の各小学校区の高齢者やご家族を支援するため、新たな地域包括支援センターを、南栄町の高齢者福祉施設内に開設します。
高齢者外出支援では、制度の見直しと共に、協力店の情報などを掲載した冊子を配布し、特典を付与するなど、高齢者が外出を楽しめる機会を創出してまいります。
重点施策3「子育て・教育」
次に、重点施策の3項目め、「子育て・教育」については、令和8年度も、引き続き、注力すべき施策と考えています。
「子育て」に関しては、共働き世帯の増加などによって、高まる保育需要に応えるため、北原山町と旭前町に、新たに民間保育園2園を開園します。
また、本年4月から全国で本格実施される、「こども誰でも通園制度」を開始するほか、保育士の処遇改善や、空調設備の改修を進め、保育環境の充実を図ります。
その他の子育て支援では、民間の放課後児童クラブに対する物価高騰対策支援や、児童福祉施設運営事業者への省エネ設備導入・更新支援のほか、名古屋市との病児・病後児保育施設の相互利用を実施します。
「教育」に関しては、中学校に引き続き、全ての小学校体育館に空調設備を設置するための設計を実施します。また、三郷と渋川の各小学校のエレベーターを改修するほか、5つの小学校のロッカー改修や、小中学校の照明LED化など、安全かつ質の高い教育環境の整備を、着実に進めてまいります。
いじめ・不登校対策については、小学校低学年の学習支援を行う教員を、4月から各校に1名ずつ配置し、新たな不登校を生まない体制を整備すると共に、中央公民館内の教育支援センターを拡張し、登校が難しい児童生徒の支援を進めます。
学校給食に関しては、国の交付金などを活用して、小学校給食費の無償化を開始すると共に、中学校給食費では、食材費の高騰分の公費支援を継続実施し、子育て世帯の経済的負担を軽減します。
また、生涯学習については、県内有数の天体望遠鏡を有する、スカイワードあさひ天体観測室の利活用を促進し、尾張旭の魅力増進を図ります。
そのほか、中学校の休日部活動では、指導体制の整った種目から、地域クラブ活動へ移行すると共に、図書館や総合体育館、文化会館の長寿命化対策工事や設計などを計画的に実施します。
重点施策4「経済・多様性」
次に、重点施策の4項目め、「経済・多様性」についてです。
「経済」に関しては、国の経済対策の交付金を活用した事業者支援などを行いながら、商工会や農協、観光協会、ハローワーク瀬戸などの関係団体と連携し、地域経済の活性化を推進します。
市民の皆さまへの物価高騰対策としては、一人あたり5,000円分のギフトカード型商品券を配付し、食料品などにかかる経済的負担を軽減します。また、この商品券の市内での利用促進を図るため、小規模企業などのデジタル化を支援します。
事業者への支援としては、自動化・省力化、業務改善につながる設備導入に対する支援を、新たに実施します。このほか、ニーズに応じ、工場の新増設等への支援や、事業承継相談会の開催などに取り組みます。
また、「おいしい紅茶のまち」の取組を推進するため、観光展や催事に参加して、「尾張旭の魅力ある商品」のPRと共に、市内外への情報発信に努めます。
農業振興については、農業振興地域整備計画の見直しにより、効果的かつ着実な事業の推進を図るほか、次世代を担う人材を育成・確保するための新規就農者支援を継続します。
次に、「多様性」に関しては、多文化共生社会の取組として、災害時外国人支援に関するワークショップを開催し、多文化防災の土台づくりを進めます。
愛知万博のフレンドシップ国であるトンガ王国との交流では、新たにJICAと連携した小学校での授業を実施し、関係性の継続と充実を図ります。
また、アジア・アジアパラ競技大会を契機として、アジア各国・地域との友好を深めるため、アジア料理イベントを開催します。
重点施策5「環境・都市基盤」
次に、重点施策の5項目め、「環境・都市基盤」についてです。
「環境」に関しては、地球温暖化対策を推進するため、家庭や事業者等の省エネ家電・設備の導入、更新を支援します。
公共施設については、照明のLED化を計画的に進め、温室効果ガスの排出抑制に努めます。
また、公園・緑地では、大久手西公園の改良工事を実施するほか、北原山2号公園の整備に着手します。矢田川河川緑地については、市内外の多くの方に活用してもらえるよう、駐車場を整備し、その魅力を広く周知してまいります。
「都市基盤」に関しては、三郷駅周辺まちづくり事業の進展により、建物の解体工事や建築工事に着手する段階に入ることから、引き続き、組合や市民、事業者の皆さまと一致協力して、着実な前進に注力します。
北原山土地区画整理事業では、事業開始から25年が経過し、道路やまちの整備が進んだことで、課税の公平性の観点から、利用実態に即した固定資産税・都市計画税の仮換地課税を開始します。一方で、未整備の箇所については、良好な住環境をつくるため、事業完了に向け、引き続き、組合を支援してまいります。
また、印場駅北側において、エレベーターの設置や駐輪場・乗降所・歩道の整備など、バリアフリー化を推進し、駅利用者の安全確保と、利便性向上を図ります。
このほか、三郷橋・三郷橋歩道橋の改修工事や、旭前町における雨水排水整備工事などを実施します。
上下水道事業では、水道管の耐震化と下水道管の布設工事を着実に推進すると共に、経営の更なる効率化に努め、持続可能な事業運営を行ってまいります。
重点施策6「共創・行政経営」
最後に、重点施策の6項目め、「共創・行政経営」についてです。
「共創」に関しては、地域集会所の空調設備更新や、照明のLED化の補助金により、自治会・町内会の負担軽減を図ります。
冒頭でも触れた、市民祭などのお祭りについては、統合・拡充を図り、会場を愛知県森林公園に移して、「あさひフェスタ」として開催をいたします。より「楽しさ」と「にぎわい」を創出するイベントとなるよう工夫を凝らし、地域と共に盛り上げてまいります。
次に、「行政経営」では、市役所などの開庁時間について、職員の働き方改革や、より質の高い行政サービスの提供につなげるため、時間の短縮を実施します。併せて、所得課税証明書のコンビニ交付や、粗大ごみ収集予約のLINE受付など、オンライン申請による来庁不要な手続きの拡充により、市民サービスの向上を図ります。
このほか、効率的な行政事務のため、生成AIの活用を進めると共に、職員の「ハラスメント相談窓口」を開設して、働きやすい環境を整えます。
なお、平子町北地内市有地については、長年に亘り利活用の可能性を模索してきたものの、残念ながら手詰まり感が否めません。不審火や有害鳥獣のリスクもあり、可能な限り早期の対処が必要です。問題を先延ばしすることなく、民間のアイデアや資金力の活用を検討し、対処の方向性を見出していきます。
行政改革に関しては、職員の提案による様々な取組が始まっています。従来からのチャレンジ事業や、昨年始まった「稼ぐ!プロジェクト」は、私が職員に向けて発信し続けてきた「風通しのよい、チャレンジする職場風土」への意識改革が、確実に根付いてきた証であると、嬉しく思っています。
本市の財政状況は、昨今の物価・人件費の急激な高騰による経常経費の増加により、財政調整基金の大幅な取崩しが必要で、この状態が続けば、数年後には基金が底をつく恐れがあります。この状況を打開し、財政の健全性を担保するためには、先手を打つことが必要と考え、「行財政基盤集中改善プロジェクト」を、昨年11月に立ち上げました。
改善目標額を5億円に設定し、「事務事業の見直し・廃止」、「公共施設の整理・統合」、「行政組織・人事の見直し」、「低未利用地の売却・貸付」、「受益者負担の見直し」など、年末までの短期集中で取り組んでまいります。
こうした厳しい財政状況に直面する中、行政の継続性の重みを痛感しています。本市の特色ある行政サービスを提供し続けるため、自身の民間企業経営の知見も踏まえ、生き残りを賭けた工夫に知恵を絞ってまいります。
おわりに
以上、重点施策の概要について、ご説明を申し上げました。
時の流れは早いもので、昨年の3月定例会初日は、退院後の初登庁直後のため、体調への配慮をいただき、施政方針を文書でお伝えしました。その頃に想いを馳せますと、今回、市政のテーマとした「楽しく健やかな暮らし」は、何物にも代え難い大切なものです。何気ないごく普通の暮らしの中にこそ、幸せや楽しみがある、そのことを、心の底から感じています。市民の皆さまの日常の「暮らし」を支え、守ることが、市長としての私の責務であると、改めて実感をしています。
私は、自身のふるさとでもある尾張旭市のさらなる発展のために、何が必要なのかを、一市民としての目線、長年培った企業人としての目線、そして市政の舵取りを担う市長としての目線で、当初から真摯に問い続けてまいりました。市民の皆さまに「住み続けたい」と思ってもらえるまちとなること、そして、他市町の皆さまから終の棲家として「住みたい」と選んでもらえるまちとなること、それこそが、目指すべき姿であると確信をしています。
市長就任の初年より、多くの施策の種をまき、2年目にはそれが芽を出し、3年目には枝葉を伸ばし、一部ではありますが、花が咲き、実を結ぼうとしています。大切に育ててきた様々な施策が、着実に形になりつつあります。市民の皆さまと共に、これらの取組の成長と変化を楽しみ、近い将来、その果実が収穫できる時を、大いに期待を持って迎えたいと願っています。
私の推し進めるまちづくりによって、シビックプライドの向上を図り、市民の皆さま一人ひとりが、尾張旭市に誇りと愛着を抱き、可能であれば、地域に貢献しようとする意識を持っていただけることを願い、職員一同、一丸となって、各施策を推進してまいります。
結びに、市民の皆さまや、議員各位の多大なるご理解とご協力を心からお願い申し上げ、私の施政方針とさせていただきます。