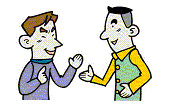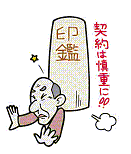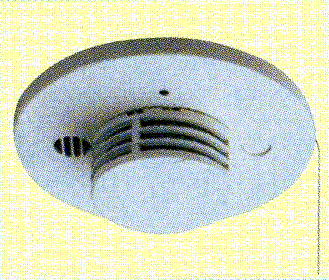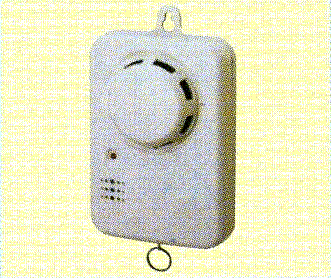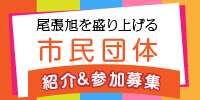ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
住宅用火災警報器を設置しよう
法改正と条例改正
平成16年6月に消防法が変わり、一般の住宅にも火災警報器が必要となりました。(消防法第9条の2、消防法施行令第5条の6~第5条の9)
これを受けて、尾張旭市火災予防条例も平成17年9月議会で改正が可決され、平成17年10月5日に公布、平成18年6月1日に施行されました。(尾張旭市火災予防条例第29条の2~第29条の7)
- 戸建住宅、併用住宅、共同住宅、寄宿舎などすべての住宅が対象です。
- 住宅用防災警報器(一般的に「住宅用火災警報器」といいます。)または住宅用防災報知設備(一般的に「住宅用自動火災報知設備」といいます。)を設置することとなりました。
- 自動火災報知設備またはスプリンクラー設備等が設置されている場合は必要ありません。
- 住宅の関係者(所有者、管理者、占有者)に設置義務があります。持ち家の場合は所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。
- 平成18年6月1日から設置義務が生じました。
設置効果
近年、住宅火災で夜間就寝中に「逃げ遅れ」によって命を落とすケースが多くみられますが、火災を早く察知し、避難することにより、命が助かる可能性は高くなります。アメリカやイギリスでは、住宅用火災警報器の設置が義務付けられており、住宅火災の死者数が半減するなど効果を上げています。
種類
- 大きく分けて「煙」に反応するタイプ(煙式)と、「熱」に反応するタイプ(熱式)があり、法的に設置するのは「煙式」です。
- 電池式と家庭用電源式(100ボルト)があります。
- 単独鳴動型と連動型があります。
- 天井に設置するタイプと壁に設置するタイプがあります。
- メーカーにより形状や機能が異なります。
- 複合型(煙式+都市ガス)警報器等もあります。
|
天井タイプ |
壁タイプ |
|
|---|---|---|
|
|
|
|
設置する部屋
寝室
- 普段の就寝に使われる部屋に設置します。
- 子供部屋や高齢者の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。
3階建て以上の場合
- 寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。(この階段の上階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
- 寝室が避難階(1階)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
その他
- 住宅用火災警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7平方メートル以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
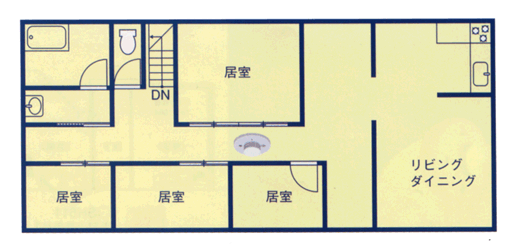
- 台所の設置は義務ではありませんが、火災の原因となりやすい場所なので、出来る限り設置をしていただくようお願いします。
取付け位置
天井に設置する場合
- 警報器の中心を壁から0.6m以上離して取り付けます。
- 梁などがある場合は、梁から0.6m以上離して取り付けます。
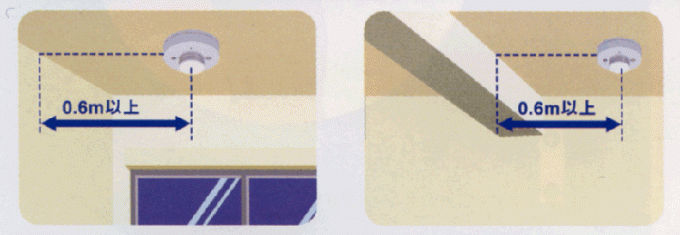
- エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。
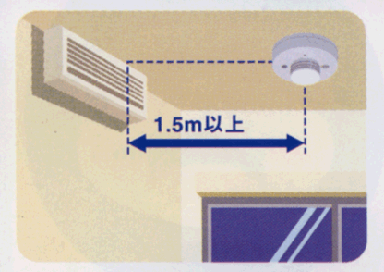
壁に設置する場合
- 警報器の中心が天井から0.15~0.5m以内の位置に取り付けます。
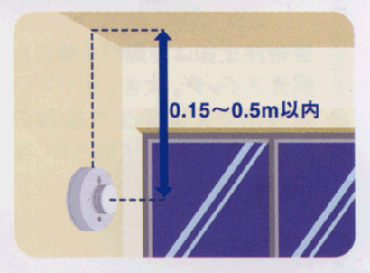
タイプ別設置例
1階建て
寝室1階
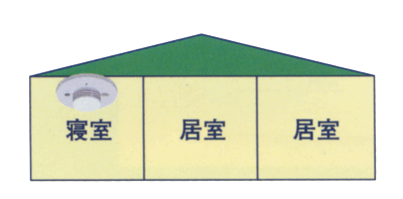
寝室1階のみ
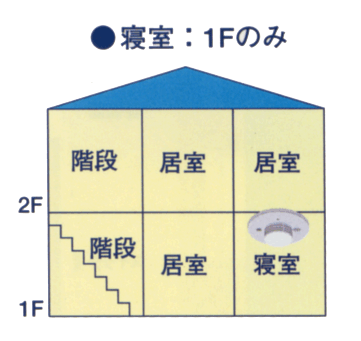
寝室2階のみ
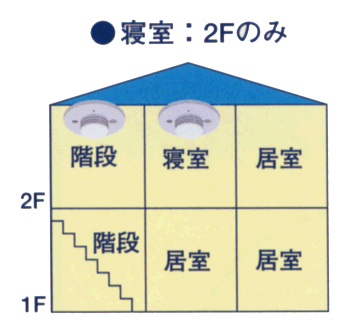
寝室1・2階
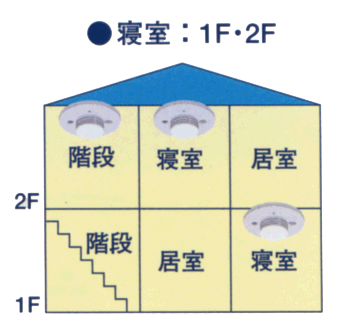
寝室1階のみ
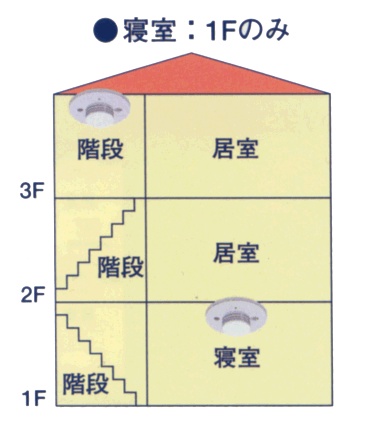
寝室2階のみ
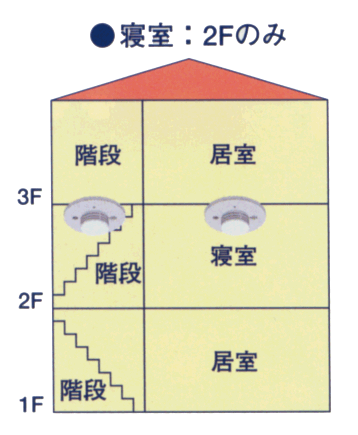
寝室3階のみ
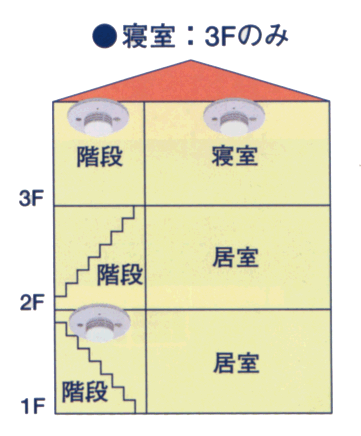
寝室1・2階
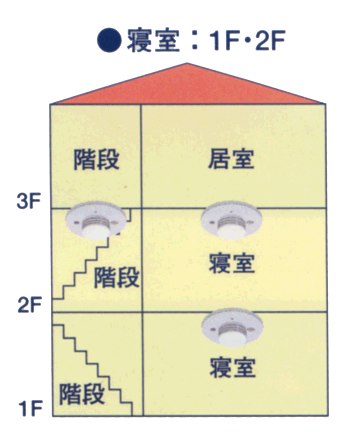
寝室1・3階
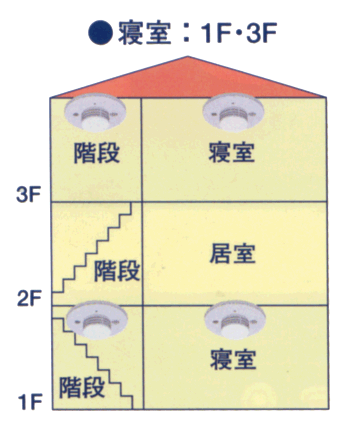
寝室2・3
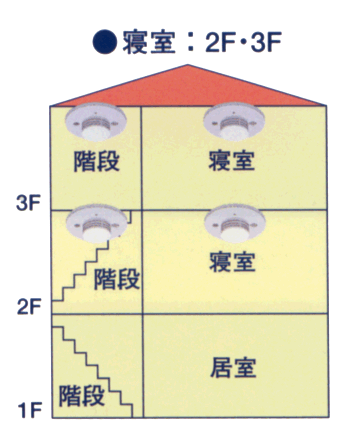
寝室1・2・3
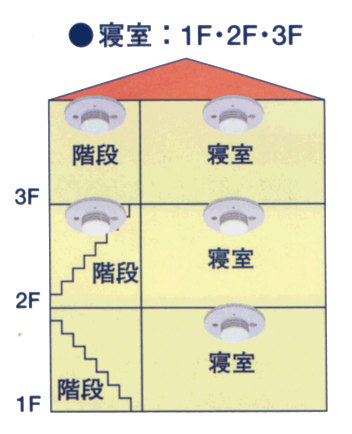
警報器が鳴ったら
対処の一例
- 高齢者や子ども、障害を持っている方はすぐに避難する。
- 火災か誤作動か確認する。・・・確認に部屋に入る際、周辺の壁やドアノブが熱くなっているようなときは、扉を開けると室内が一気に(爆発的に)燃える可能性があります。そのときは、避難を優先させます。
火災の場合
- 大声で周囲に「火事だ!火事だ!」と2回以上叫びます。(1回だけでは、聞き漏らしや何を言っているかわからないことがあります。)
- 119番通報します。(近くに人がいるときは頼んでもいいでしょう。)
- 発見が早く、気持ちに余裕があり、火が天井に燃え移っていなければ消火器で初期消火します。自信がないときは、避難してください。

誤作動
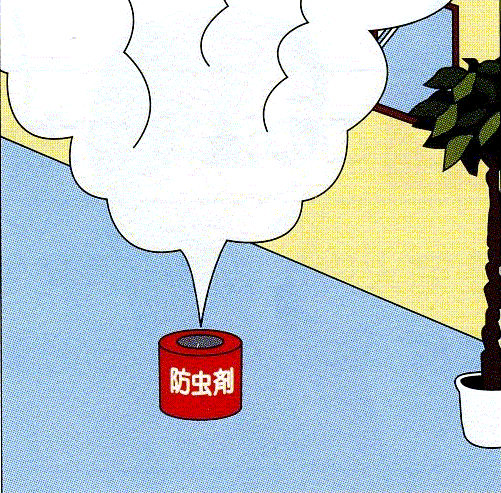
- 煙に反応して火災発生を知らせるため、感知する精度の高さから、誤作動をおこしてしまうこともあります。
しかし、安易に誤作動と決め付けずに、万一の場合を考えてよく確認してください。なお誤作動が確認できたら、警報音を止めて、家庭内や近所に火事ではないことを知らせます。 - 一般的には、日常の喫煙で作動するようなことはありませんが、直接煙をかけるようなことがあれば誤作動の原因となります。
- 煙の出る殺虫剤などに反応することがあります。
- それぞれの機器使用上の注意をご覧ください。
価格
価格は、メーカ、種類、機能等により異なりますが安いものだと2,000円前後から、無線連動型等、音が鳴ること以外にもいろいろな機能が付加されているものだと10,000円前後で販売されています。
点検方法
- 業者による点検義務はありません。いざというときのために、ご家庭で点検、手入れをしましょう。
- 作動点検・・・定期的(1ヶ月に1回程度)に火災警報器が鳴るかどうかテストしてみましょう。(本体についているボタンやひもを引くと音が鳴ります。)
- 機器が古くなったら交換・・・電池式のものは電池を交換してください。ただし機器の交換目安はおおむね10年とされていますので、10年を越えたものは機器ごと交換することをお勧めします。なお、機器に交換目安のシールが貼ってあるものや、電池の容量が少なくなると「ピー」という音などで知らせるものもあります。
販売場所等
- 消防署では販売していません。家電量販店や防災業者等で購入できます。
- 購入時の目安として、住宅用火災警報器には、国の定める技術上の規格があり、その規格に適合する製品には合格の表示がされています。

検定 マーク
悪質業者にご注意
- 訪問販売等の悪質な業者によるトラブルにあわないように次のような手口にはご注意ください。
- 消防職員や、市役所職員、消防団員などを装い販売するケース・・・消防職員など公共機関の職員のような服装や言動で訪問し「消防署の方から来ました。各家庭に住宅用火災警報器をつけなくてはなりません。」と言って売りつける。(※消防職員や、市役所職員、消防団員などが住宅用火災警報器を販売することはありません。)
- 市役所、消防署などの委託を装い販売するケース・・・「市役所(消防署)の依頼でまわっています。住宅用火災警報器が必要です。」と言って売りつける。(※市役所、消防署などが特定の業者に販売を委託することはありません。)
- 火災予防条例などの条文を使い、設置をせまるケース・・・火災予防条例などの条文を見せ、「この条文のとおり、設置しなければならないことになったので、すぐに取り付けてください。」と言って売りつける。(※平成20年6月1日からすべての住宅に設置が義務化になっています。詳しくは「法改正と条例改正」をご確認ください。)
- 特典があるような口ぶりで契約を急がせるケース・・・「今だけ」「あなただけ」などと特別な思わせぶりで売りつける。(※価格や機能はさまざまです。内容をよく検討し、他の業者からも見積もりをとって比較するなど、十分に考えましょう。)
- 火災警報器は、購入後の無条件解約の申出(クーリング・オフ)の対象となっています。場合によっては、無条件で解約できることもあります。消費生活相談窓口にご相談ください。