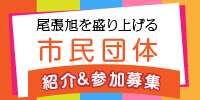本文
避難方法について
「避難」とは、「難」を「避」けることであり、小中学校や公民館などの避難所に行くことだけが避難ではありません。
「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自宅の災害リスクととるべき行動を確認しましょう。
避難方法の種類
在宅避難
メリット
- プライバシーの確保ができる
- 住み慣れた環境で生活できる
- 感染症のリスクが低い
デメリット
- ライフラインが使えない場合、自力では対処できないことがある
- 支援物資や情報が届きにくい
ポイント
家庭で備蓄をしておく
市でも災害用備蓄をすすめていますが、命をつなぐ最低限の用意しかありません。また、災害の規模が大きくなればなるほど、市からの支援の手が届かないこともあります。
災害時でも安心して生活するために、各家庭で災害用備蓄の準備をお願いします。
「災害時の備蓄品について」のページを参考に、各家庭で必要なものを考えてみましょう。
指定避難所に避難者として登録する
自宅で避難生活を送っている方で、断水によってトイレが使えなくなったり、災害時にスーパーマーケット等が休業していて飲食料が手に入らないなど、物資が不足する場合には「避難所利用者登録票」を指定避難所に提出することで、市からの支援(支援物資の配布など)を受けることができます。
支援物資の受け取りについては、指定避難所に直接来てもらう必要があるため、自宅から近い指定避難所に提出することをおすすめします。
情報や支援物資は指定避難所で受け取る
市内にある指定避難所(市内小中学校12か所)をその地区の防災拠点として、情報発信や支援物資の集積・配布場所とします。
支援物資は「避難所利用者登録票」を提出した指定避難所へ受け取りに行き、張り出されている情報等を確認しましょう。
縁故避難
メリット
- プライバシーの確保ができる
- 災害の影響を受けない場所であれば、ライフラインが使用できる
- 話し相手がいる
デメリット
- 家主に気を遣う
- 居住地付近の被災状況等の情報が入りにくい
ポイント
事前に約束をしておく
避難先になり得る相手方と、日頃からコミュニケーションをとり、お互いにいざというときに避難し合えるような約束と関係づくりをしておきましょう。
近くに住む方だと、災害時には同じように被災している可能性が高いため、なるべく災害の影響が少ないと考えられる離れた地域の方がよいです。
状況がひどくなる前に出発する
災害発生後、「様子を見てから出発しよう」と時間をおいてしまうと、
- 外部からの救援車両等で交通量が増え、目的地への到着が遅くなる
- 被災地で一定期間生活を送ることで心身ともに疲弊し、避難する気力がなくなってしまう
といったことが多くあります。
そういったことを避けるために、縁故避難をする際には早めに出発することを心がけましょう。
居住地の自治体ホームページ等をこまめに確認する
居住地の情報が手に入りにくいため、ライフラインの復旧状況が分からなかったり、家屋の被害認定調査の申請が遅れてしまったりすることがあります。
発災直後からしばらくすると、ライフラインの復旧状況や、市の支援情報などが自治体ホームページなどに掲載されます。
自宅に戻るタイミングや、必要な手続きを確認するため、こまめに居住地の自治体のホームページを確認しましょう。
その他防災情報を配信するアプリ等があれば、そちらも登録しておくと情報が入手しやすくなります。
尾張旭市の情報収集方法については、「防災情報を手に入れよう」のページをご確認ください。
ホテル等への避難
メリット
- プライバシーの確保ができる
- 災害の影響を受けない場所であれば、ライフラインが使用できる
- 感染症のリスクが低い
デメリット
- お金がかかる
- 居住地付近の被災状況等の情報が入りにくい
ポイント
滞在期間を想定し、お金の準備をする
仮設住宅等への避難とは異なりますので、ホテルなどへの滞在費用は被災者の方の実費負担となります。
どの程度の期間避難するかなどを事前に決めておき、いざというときにすぐに持ち出せるよう、非常用持出袋に必要な現金を入れておくなど準備をしておきましょう。
状況がひどくなる前に出発する
縁故避難と同様です。
災害発生後、「様子を見てから出発しよう」と時間をおいてしまうと、
- 外部からの救援車両等で交通量が増え、目的地への到着が遅くなる
- 被災地で一定期間生活を送ることで心身ともに疲弊し、避難する気力がなくなってしまう
といったことが多くあります。
そういったことを避けるために、早めに出発することを心がけましょう。
居住地の自治体ホームページ等をこまめに確認する
縁故避難と同様です。
居住地の情報が手に入りにくいため、ライフラインの復旧状況が分からなかったり、家屋の被害認定調査の申請が遅れてしまったりすることがあります。
発災直後からしばらくすると、ライフラインの復旧状況や、市の支援情報などが自治体ホームページなどに掲載されます。
自宅に戻るタイミングや、必要な手続きを確認するため、こまめに居住地の自治体のホームページを確認しましょう。
その他防災情報を配信するアプリ等があれば、そちらも登録しておくと情報が入手しやすくなります。
尾張旭市の情報収集方法については、「防災情報を手に入れよう」のページをご確認ください。
避難所避難
みなさんがイメージすることの多い指定避難所への避難となります。
尾張旭市の指定避難所の詳細は「指定避難所について」のページをご確認ください。
メリット
- 支援物資や情報が届きやすい
- 話し相手がいる
デメリット
- プライバシーの確保が難しい
- 様々なルールがある
- 感染症のリスクが高い
ポイント
基本的な感染対策を行う
指定避難所には多数の方が避難してくることが予想され、人が多くなればなるほど、感染症のリスクが高くなります。手洗いうがいや手指消毒、マスクの着用等の基本的な感染対策を行いましょう。
ただし、災害時には断水により手洗いができなかったり、物流機能の停止により消毒液などが手に入らないこともあります。消毒液やウエットティッシュ、マスクなどの備蓄があると安心です。
非常持出用袋などを用意する
みなさんが指定避難所で生活できるよう、市でも備蓄品などの用意をしていますが、必要最小限の用意しかありません。
自分の命は自分で守る「自助」を基本に、避難に必要なものは事前に用意しておきましょう。
とくに眼鏡や普段から飲んでいる薬などの自分だけが必要なものは、事前予備を用意しておくことをおすすめします。
トラブル防止のためルールを守る
集団生活の場となります。トラブルを防止するため、決められたルールは必ず守りましょう。
避難者同士助け合って生活する
指定避難所は避難者による自主運営が基本です。掃除、支援物資の受入や配布、炊き出しの準備など避難者全員が自分が出来ることを行いながら、協力して生活しましょう。
車中泊避難
近年の災害では、プライバシーの確保の観点や子どもやペットと一緒に避難するために、「車中泊避難」を選ぶ方も多くなっています。
しかし、車内などの狭い空間で長時間過ごすことで「肺塞栓症(エコノミークラス症候群)」を発症し、命を落とす事例も少なくないことから、尾張旭市では車中泊避難を推奨しておりません。
もしやむを得ずに車中泊避難を行うことを考えている場合は、「車中泊避難GUIDEについて(あいち・なごや強靭共創センター) 」などを参考に、事前の準備や気を付けるべきことを確認しましょう。
避難所利用者登録票について
指定避難所に避難する場合はもちろん、避難所以外の場所で避難生活を送る場合も「避難所利用者登録票」を提出しておくことで、市からの支援を受けることができます。
いざというときに備え、事前にダウンロードし、あらかじめ記入できる項目を記入しておきましょう。