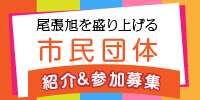本文
避難について
「避難」とは、「難」を「避」けることであり、小中学校や公民館などの避難所に行くことだけが避難ではありません。
「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自宅の災害リスクととるべき行動を確認しましょう。
避難所・避難場所とは
市では、大雨による浸水やがけ崩れ、地震などの大規模災害に備え、あらかじめ避難所や避難場所を指定しています。
避難所・避難場所は、災害の種類や役割によって異なります。
いざというときに慌てないように避難所・避難場所の位置や役割をあらかじめ確認し、そこに安全に行くための経路も日頃から考えておきましょう。
指定緊急避難場所
命を守るために、災害の危険から一時的に避難するための場所です。
一時避難場所
地震災害において、一時的に安全を確保するため避難する場所です。市では、市内の公園などを一時避難場所として指定しています。
市が指定している場所が家の周りにない場合は、上から物が落ちてこない場所(田・畑・駐車場など)に避難しても構いません。
地域避難所
風水害(洪水や内水氾濫、がけ崩れなど)時に、命を守るために短期間避難するための場所です。
地域避難所は、大雨警報や暴風警報の発令、台風の進路などの気象情報をもとに、必要に応じて市が開設を判断します。
小学校区に1つずつ、全9か所を市の地域避難所として指定しています。
指定避難所
指定避難所
地震災害時、または風水害時に甚大な被害が発生し、一定期間避難者が生活を行うための場所で、必要に応じて市が開設します。
市では、市内すべての小中学校(全12か所)を避難所として指定しています。
また、小中学校体育館の収容人数を超えるおそれがある場合、公民館等を二次的に開設する場合があります。
その他、大規模地震によって帰宅困難者が大量に発生した場合は、総合体育館を帰宅困難者のための避難所として開設する場合があります。
福祉避難所
避難生活において特別な配慮が必要とされる方(介護が必要な方、妊娠中の方、乳幼児、障がいのある方など)のための避難所となります。
市では保健福祉センターを指定していますが、民間社会福祉施設などと災害時の施設利用についての協定を締結し、必要に応じて避難者を受け入れていただきます。
原則、福祉避難所に直接避難することはできませんので、まずは近くの指定避難所への避難をお願いします。
避難行動が必要な場合
地震災害
自宅等の柱が傾いていたり、梁などに亀裂が入っていて建物が倒壊する恐れがある場合や、土砂災害のおそれがある地域に住んでいる場合は避難してください。
自宅に被害がとくにない場合、または軽微な損傷の場合は、そのまま自宅で避難生活を送る「在宅避難」という避難方法もあります。
避難のタイミング
地震は急に発生します。揺れが続いている間は机の下などにもぐって身の安全を確保し、揺れが収まった後、危険がある場合に避難します。
地震が発生した時の行動については、「地震発生直後の行動」のページをご確認ください。
風水害
ハザードマップなどで自宅周辺のリスクを確認し、浸水や土砂災害などのリスクが想定されている場合は避難してください。
安全な場所にいる場合(災害リスクが想定されていない場所など)は、災害時にあえて外出しないなど、自宅等に留まることで安全を確保することができます。
事前に避難行動判定フローで避難のタイミングを確認したり、マイ・タイムラインを作成することで、いざというときに慌てずに行動することができます。
洪水などによる浸水被害については、建物の2階に避難する「屋内安全確保(垂直避難)」をすることも可能です。
ただし、土砂災害の危険がある場合には、建物ごと飲み込まれてしまう可能性があるため、危険区域外への「立ち退き避難(水平避難)」をしてください。
避難のタイミング
市が発令する「避難情報(警戒レベル)」に合わせて避難しましょう。もちろん、市が避難所を開設したタイミングなどに前もって自主的に避難していただくこともできます。
ただし、豪雨時や夜間に自宅外へ避難することは大変危険です。こまめに情報収集を行い、早めの避難を心がけましょう。
避難情報(警戒レベル)の詳細は、「防災情報と警戒レベル」のページをご確認ください。
避難行動要支援者について
災害が起きたとき、自分だけでは自分の命を守るための行動をとることが難しく、一人で避難することが困難な方を「避難行動要支援者」といいます。
災害時は、地域での助け合いがとても大切です。避難する際に余裕があれば、近く住んでいる避難行動要支援者に声をかけ、どんな支援が必要かを確認し、一緒に避難をお願いします。
詳細は、「避難行動要支援者に対する援助」のページをご確認ください。
要配慮者利用施設の所有者・管理者様へ
浸水想定区域内、及び土砂災害警戒区域内の要配慮者施設の所有者または管理者には、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられています。
詳細は、「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について」のページをご確認ください。
避難方法について
避難には市が指定する避難所・避難場所に避難することはもちろん、自宅内で避難するなど、様々な方法があります。各家庭にあった避難方法を考えておきましょう。
詳細は、「避難方法について」のページをご確認ください。