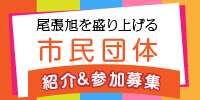本文
【おわりあさひレポート】12月のイベント・行事
おわりあさひレポートでは、毎月10日と20日にまちの話題をお届けします!!
あなたの思いを伝えるベンチ 寄附第1号が設置されました!
矢田川河川緑地に、市内の造園業者である株式会社アサヒグリーンから、初めてのベンチ(背付き)の寄附を受け、設置された。今回の寄附は、市が令和6年8月から開始したベンチ寄附事業により行われたもの。


年末年始は火の用心 少年少女消防団による防火啓発活動
12月23日(月曜日)午後5時から、市内の商業施設で少年少女消防団による防火啓発活動が行われた。
この活動は、年末年始における火災を予防するために行われているもので、この日は少年少女消防団12人が参加し、商業施設を訪れた方に「火事に気を付けてください」と声をかけながら、チラシを手渡して啓発した。
参加した団員の旭小学校5年生の川嶋 樹羅(かわしま じゅね)さんは、「年末年始は、特にたばこの不始末に気を付けてほしい。あと、火災報知機は設置してから10年が交換の目安なので、大掃除をするこの機会に、確認してほしい」と語った。
また、この日は啓発活動の前に、令和7年1月12日(日曜日)に開催される消防出初め式の練習も行われ、児童らは、消防職員の指導を受けながら、初期消火や傷病者搬送、救命処置などの動きを確認していた。
訓練会場内では、大きな声で「よし」という返事が響き渡り、当日に向けての気合が感じられた。
家庭教育学級(たんぽぽ)第3回合同学級 名門吹奏楽部が届けるクリスマスコンサート
12月21日(土曜日)午後1時30分から文化会館で、家庭教育学級(たんぽぽ)第3回合同学級として、愛知県立名古屋南高等学校吹奏楽部によるクリスマスコンサートが開催された。
家庭教育学級は、家庭間だけでは解決困難な問題を地域での活動を通して助け合うことなどを目的に小学校ごとに設置されているもので、普段は食育講座や親子で参加できる走り方講習会など様々な企画が行われている。
合同学級は、全校の家庭教育学級が参加する事業で、市が企画して年に3回程度開催されている。
名古屋南高等学校吹奏楽部は全国的に活躍しており、この日は、「赤鼻のトナカイ」などのクリスマスナンバーや、アニメの曲などを披露した。
また、演奏の合間にフルートやオーボエなどの楽器紹介のコーナーや、演奏中にもサンタクロースの衣装を着た生徒が観客席でクリスマスの飾りを配る一幕もあり、来場者も生徒との交流を楽しんでいた。
指揮をした野呂 直輝(のろ なおき)さんは、「会場の皆さんがとても温かい雰囲気をつくっていただき、生徒も楽しく演奏ができた。楽しんでもらえたのならうれしい」と語った。
この日は、約150人が訪れ、一足早いクリスマスを楽しんだ。
瑞鳳小でトンガ王国の暮らしや文化を学ぶ「トンガ学習プログラム」を実施
12月19日(木曜日)午後1時45分から瑞鳳小学校体育館で、NPO法人日本トンガ友好協会運営のもと、交流事業「トンガ学習プログラム」が実施された。
これは、2005年愛知万博の一市町村一国フレンドシップ事業により本市とつながりのできたトンガ王国との交流事業で、瑞鳳小学校5年生64人を対象に実施。児童らは事前にトンガ王国の基礎知識や人々の暮らし、文化を学習した上で本プログラムに臨んだ。
本プログラムは、トンガ出身で元ラグビー日本代表のラトゥ ウィリアム 志南利(しなり)さん、佐賀県職員としてトンガ赴任実績のある深川千幹(ふかがわちもと)さんをお招きし、トンガ王国の文化や食、環境をテーマに、トンガ王国が抱える問題や日本とのつながり等、児童が異文化から多様な価値観を学ぶ機会の創出を目的としている。
5時間目の授業では、トンガの文化や食、トンガの基礎知識について、トンガの主食が芋であること、「キエキエ」、「タオパラ」、「トゥペヌ」と呼ばれるトンガの正装、トンガ王国が親日国で、そろばんが小学校の授業に取り入れられていること等の説明があった。
続いて、6時間目には、環境をテーマにトンガが抱える地球温暖化などによる自然災害や海面上昇といった問題について、説明を受け、児童らは、自分たちでできるSDGsの取り組みは何かを考え、「コンビニでレジ袋をもらわない」、「ごみを減らす」、「エアコンの使用頻度を押さえる」等、各々が取り組めるSDGsを発表した。
また、休憩時間には、ラトゥさんに握手をお願いする児童やタックルを試みる児童、日本の好きなところや大変だと感じたことなどの質問を積極的に行う児童の姿も見られた。
侵入盗被害防止及び特殊詐欺被害防止啓発活動
令和6年12月19日(木曜日)、イトーヨーカドー尾張旭店において、14時から来店客などに対し棒辺啓発物を配布しながら、侵入盗被害防止及び特殊詐欺被害防止広報を実施した。市内における侵入盗については、被害認知件数こそ減少しているものの、その内の空き巣被害件数については前年からほぼ倍増。また特殊詐欺についても依然として被害は発生しており、不審な電話も後を絶たない。
歴史民俗フロアmini民具企画展「裁縫の道具」
令和6年12月19日(木曜日)~令和7年2月4日(火曜日)まで、スカイワードあさひにおいて、歴史民俗フロアmini民具企画展「裁縫の道具」を開催する。今回の展示では、足踏みミシンや裁ち台など、裁縫に関する古い道具を展示。
中学生に平和の大切さを 被爆体験「語り部」講演会
12月18日(水曜日)午後1時25分から、市立旭中学校で、被爆体験「語り部」講演会が開催され、全校生徒約830人が耳を傾けた。
本市は平成23年に「非核平和都市」宣言をし、毎年市内の中学校が持ち回りで被爆に関して聞く機会を設けている。
講演会の講師を務めた被爆体験証言者の瀧口秀隆(たきぐち ひでたか)さんは広島県の出身で、4歳のときに爆心地から1.8km離れた白島北町で被爆した。
瀧口さんは、当時の様子を写真やイラストを交えて語り、被爆した直後の自身のケガや家族の死、避難から現在に至るまでの、苦しさや悲しさを生徒たちに伝えた。
講演の最後には、「1人でも多くの人に、戦争はいけない、核兵器はいけない、ということを伝えてほしい」と、生徒たちへメッセージを送った。
2年生の中田 実乃理(なかた みのり)さんは、生徒を代表して瀧口さんへ感謝を伝え、「平和であることに感謝をして、過ごしていきたい。今日学んだことを親や友達に伝えていきたい」と、決意を語った。
日本文化(書道)を学ぼう♪
令和6年12月18日(水曜日)、中央公民館において、外国人のための日本語教室会を開催。書道歴30年で尾張旭市在住の濱畑弥生さんを講師として迎え、書道教室を開催した。
助成金で活動を広げる!市民活動促進助成事業中間報告会と各メディアで活動を広める方法!市民活動講座
12月14日(土曜日)午前9時30分から、渋川福祉センター(渋川町)で、市民活動促進助成事業にて助成金を受けている8つの市民団体が活動の進捗などを発表した。
市民活動促進助成事業とは、地域社会の発展につながる市民活動団体の活動を支援するため、審査を通った団体に助成金を交付している。
子育てや環境、音楽、スポーツなど、様々な分野の活動が中間報告され、講評では、金城学院大学教授の齊藤由香氏や認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会認定ファンドレイザーの西村健氏が、多様な世代への活動の評価や新規加入者を増やすためのアドバイスなどを行った。
中間報告会後、各メディアに活動を取り上げてもらう工夫など効果的なPR方法を、紅茶のまちおこしに尽力している堀田信幸氏が実体験をもとに講演。市民団体はメモを取るなどして興味津々に受講していた。
今年、助成金を活用して参加費を割引し新規の参加者増加に成功した尾張旭でミュージカルを作ろう実行委員会代表の片桐恵子さんは「色々な団体の活動がとても参考になる。PR方法については事前告知が課題。SNSだけでなく、様々なメディアについても今後考えていけたら」と語った。


ららぽーと愛知東郷にて尾張旭市PRイベントを開催
令和6年12月14日(土曜日)、ららぽーと東郷において、市内外に発信するため県内3か所でPRイベントを実施。紅茶の試飲や旭色などのPR、あさぴーのグリーティングなどを行った。
絵本の世界を給食で!市内保育園で初めてのブックメニュー提供
令和6年12月12日(木曜日)、市内保育園において、絵本にちなんだ食材や料理を給食に取り入れた「ブックメニュー」をしない8園で提供。西武保育園うさぎ(年少)組では、「おおきなかぶ」の読み聞かせを実施し、給食で「かぶ」を使ったカレースープを提供した。
学校給食紹介映像を配信中!
令和6年12月11日(水)から、子どもたちが普段食べている給食の調理の様子や、食べ残しの処理の様子を見ることで、食に関する感謝の気持ちを表すとともに、食品ロスをなくす目的とする「わくわく!わたしたちの学校給食~あさぴーといっしょに探検しよう~」を配信中!
動画を視聴する<外部リンク>
尾張旭外国人のための日本語教室会が令和6年度国際交流推進功労者表彰を受賞
令和6年度12月11日(水曜日)、尾張旭外国人のための日本語教室会が、令和6年度国際交流推進功労者表彰を受賞し、市長を表敬訪問した。
年末の交通安全運動 ライト・オン&飲酒運転根絶キャンペーン
令和6年12月10日(火曜日)、バロー城山店において、交通事故を防止するため、店舗入り口にて啓発物品を配布。「ライト・オン&飲酒運転根絶」を呼びかけた。
「ゼロカーボンスクール※」を支援 名古屋産業大学が気候変動アクション環境大臣表彰を報告
令和6年12月10日(月曜日)午後3時30分、名古屋産業大学の伊藤 雅一(いとう まさかず)教授と博士課程でネパール出身のプリ バヌバクタ氏、アディカリ ボハラ プジャ氏、パウデル サンジョグ氏が、令和6年度気候変動アクション環境大臣表彰の受賞を柴田市長に報告した。
この賞は、「気候変動の緩和」及び「気候変動の適応」に関する顕著な功績をたたえるためのもので、高田中・高等学校(三重県津市)と連携して実施している、国内外における「ゼロカーボンスクール※」の活動支援が評価されての受賞となった。
伊藤教授は「今回の取組は市内でも活かせると考えている。城山小学校の児童と一緒に、城山公園の二酸化炭素の測定をして、市民にフィードバックするようなことも進められれば」と話した。
また、バヌバクタ氏らは母国で子どもたちに環境に関する講義をしており、「日本は先進国なのに美しい。ネパールは環境問題があるものの、みんなの関心は薄い。今回の研究で母国に貢献したい」と話した。
※ 緑化活動による二酸化炭素吸収量の増加と、省エネ活動等による二酸化炭素排出量の削減に取り組むことで、学校生活のカーボンニュートラルを探究する活動。
JAZZ&POPSコンサート マリテス/近藤有輝ピアノトリオ 国際交流会「国際交流コンサート」を開催
12月7日(土曜日)午後1時30分から文化会館あさひのホールで尾張旭国際交流会主催、国際交流コンサートを開催した。
この催しは、日本で音楽活動をしている外国人の方による演奏やトークを通じて、相互理解を深め交流の場とすることを目的として開催している。この日は、約250人の市民らが参加した。
コンサートの第一部では、近藤有輝さん(ピアノ)、北浦 ユタカさん(ベース)、ルベン・フィゲロアさん(ドラム)3人からなるピアノトリオが演奏を披露し、参加者らはピアノの繊細でやさしい音色や、ベース&ドラムの力強い音に聞き入っていた。
第二部では、マリテス・ヤスハラさん(ボーカル)を加えた、ボーカル&ピアノトリオの演奏を披露し、会場を大いに盛り上げた。会場には、ドラムのルベンさんの出身地であるペルーからの参加者やマリテスさんの出身地であるフィリピン)からの参加者が来場し、MCから紹介されると、会場から大きな拍手が巻き起こり、音楽を通じた国際交流の場となっていた。
また、アンコールでは、マライア・キャリーの「All I Want For Christmas Is You」が披露され、会場から自然と手拍子が起こり、参加者らはジャズ&ポップスの力強いサウンドに聞き惚れていた。
参加者らは、「ジャズの生演奏を見る機会がないので、今回実際にコンサートに参加できてよかった。楽器の持つきれいで、力強い音色やボーカルの力強く、芯まで届く歌声にはびっくりした」と話した。
子ども向け 尾張旭市の馬の塔体験会
12月7日(土曜日)午前10時から城山小学校(城山町)で、「尾張旭市の馬の塔体験会」が開催され、市内在住の未就学児~小学5年生19人と保護者合わせて39人が参加した。
この体験会は、市指定無形民俗文化財「馬の塔」の楽しさを子どもたちに知ってもらい、伝統文化を身近に感じることで、後継者育成と文化財の継承を目的としており、本物の馬を実際に使用する市内初の子ども向け体験会。
参加者らは、馬の塔の歴史や現状を学んだあと、馬とポニーを使用した「駆け込み」の体験を行い、実際の馬飾りの鑑賞や記念撮影等が行われた。
駆け込みを経験した子どもたちは、「馬の手綱を引っ張る力の強さとスピードに驚いた。馬が急に走り出さないよう、驚かさないように気を付けた。」と話し、保護者らも「子どもと一緒に馬の手綱を引くことができ、貴重な体験だった。保存会の方の掛け声に合わせて、子どもたちも声を出していたのが微笑ましかった。」と体験会の感想を話した。
尾張旭市の馬の塔(市指定無形民俗文化財)
豊作のお礼や雨乞いなどのため、馬を標具(だし)と呼ばれる道具で飾り、神社に奉納する献馬行事で江戸時代から行われている。市内では4地区(新居・稲葉・三郷・印場)で伝承され、異なる標具の意匠を継承している。
-尾張旭の環境・まち・未来を考える-第22回環境フォーラム
令和6年12月7日、名古屋産業大学において、第22回環境フォーラムと題し、尾張旭の華僑・まち・未来を考えるため、環境省中部地方環境事務所地域脱炭素創生室長の新原修一郎氏らをお迎えし、講演を行った。
教育分野における連携協力に関する協定の締結式
令和6年12月4日(水曜日)午前10時15分から、尾張旭市教育委員会と愛知県立大学との教育分野における連携協力に関する協定の締結式が開始された。
市教育委員会と愛知県立大学は、平成28年に「学校で教育活動支援を行うボランティア学生の派遣及び学校で行うインターンシップに関する協定」を締結するなど、様々な連携を行ってきた。
今回の協定は、より幅広い教育分野で連携協力を行うことにより、教育・研究の充実と地域社会の発展に寄与するために締結するもの。
締結式には、三浦 明(みうら あきら)教育長や、愛知県立大学の川畑 博昭(かわばた ひろあき)学長らが出席し、協定書を取り交わした。
締結式の中で三浦教育長は「協定を締結させていただくことは大変心強く、今後の地域社会の発展にも大きく貢献するものと期待している。互いに実りある協定にしていきたい」と話し、川畑学長は「今回の協定を機に、大学と市の交流を加速させていきたい。県大は、海外との連携・交流が多い。日々の生活も多国籍化していく中、市側とも国際的な交流や相互協力ができれば」と話した。
今後は、大学生による小中学校の教育活動支援や教職員要請における協力などを進めていく予定。
列車事故対応訓練
令和6年12月3日(火曜日)午前9時から、名古屋鉄道尾張旭検車支区(向町)で、市消防と名古屋鉄道株式会社により、列車事故対応の合同訓練が実施された。
これは、実際にあった列車事故の事案などを教訓にし、救助隊がレスキュー時に注意すべき点などを列車のプロである名古屋鉄道職員から学び、連携して要救助者を迅速かつ安全に救出するために実車両を用いて行うもの。
訓練は、まず名古屋鉄道職員から、列車の構造や線路上でのレスキュー時の注意点、連携方法などについて指導を受け、実車両を使って実際に事故が起こった想定で、下敷きになった要救助者を安全に救出する訓練を行った。
車両下に入った救助隊は、狭い空間の中で要救助者を一番安全に救出するための方法を模索しながら、指揮隊と連携しながら刻一刻と変わる状況に対応して救出を行った。
その後、車両のジャッキアップ訓練では、油圧式と空気式のジャッキを状況に応じて使い分けながら車両を持ち上げた。脱線しないよう、慎重に作業する様子が伺えた。
消防隊員は、「実車両を使って行うということがとても経験になる。若い隊員が多く参加したため、技術の継承にもつながり、非常に有意義な訓練となった。」と話した。また、名古屋鉄道職員は、「列車事故では市との情報共有が非常に大事になる。情報連携を密にしながら対応していきたい。」と話した。
女性部会から手縫いぞうきんなど寄贈
令和6年12月2日(月曜日)午後1時30分、公益社団法人瀬戸旭法人会が、手縫い雑巾とタオルを寄贈するため市役所を訪れ、柴田浩市長に雑巾200枚、タオル100枚を手渡した。
来訪したのは、女性部会副部会長 金谷津由子さん(かなや つゆこ)ら4名。女性部会は、社会貢献活動の一環として、毎年この時期に管内の瀬戸・尾張旭市の福祉担当課などを通して、部会員による手縫い雑巾を福祉施設などに寄贈する活動を続けており、今年で33回目となる。
金谷副部会長が「会員の高齢化が進み、作れる枚数も少なくなってきたが、1年がかりで作っているため、いろいろな施設で使ってもらえたらうれしい。」と話すと、柴田市長が「毎年、時間を掛けて作成いただき本当にありがとうございます。手縫い雑巾を使用している施設などからは、使いやすいと評判もよく、大変喜ばれています。ご無理のないように、長く続けていただけたらうれしいです。」とお礼を述べた。
JICA国際研修性が「元気まる測定」を体験
令和6年12月2日(月曜日)午前9時30分、JICA(独立行政法人国際協力機構)の国際研修生が保健福祉センターを訪れ、本市の健康都市の取組や、個々にあった保健指導を行うための測定方法である「元気まる測定」について学んだ。
これは、市の健康都市の取組が世界的に評価されていることから、JICA側が市に打診をして実現したもの。
参加した研修生は、エジプトやインドなどの医師や医療機関などに従事する12名。
この日、研修生たちは、健康都市の取組や、生活習慣病予防の対策について説明を受けた後、実際に、握力測定や片足立ちを2分間維持するなどの元気まる測定を体験した。
最後の質疑応答の時間では、参加者から「健康無関心層への周知はどのようにしているのか」、「健康に関するイベントなどはあるのか」などの質問があり、市の保健師がスーパーやドラッグストアなどで測定を行っていることや健康フェスタを紹介すると、驚いた様子を見せていた。
研修生を引率したJICAの斉藤さんは、「尾張旭市の健康都市の取組は、健康についての制度や方針がしっかりできており、世界的にも珍しい」と話していた。
あさぴースマイル給食28
令和6年12月2日(月曜日)、尾張旭市内小中学校において、月に二回実施している「あさぴースマイル給食(8大アレルゲン除去)」に加え、副食からアレルゲン特定原材料など28品目を除去した「もっと!あさぴースマイル給食28」が配食された。
全児童生徒が同じ給食を食べることにより、食物アレルギーに対する理解を深めることができた。
祝!あさぴー20周年!あさぴートレイン運行開始とお誕生日会開催
12月1日に、市イメージキャラクター「あさぴー」が誕生から20周年を迎え、通称「あさぴートレイン」の運行開始を記念したは発車式と、あさぴーの誕生日会が開催された。
出発式は、午前9時5分から尾張旭駅で行われ、柴田浩市長と連携して紅茶の普及に取り組むキリンビバレッジ株式会社の執行役員中部圏統括本部長小林雅敬(こばやし まさたか)氏があいさつした。
その後、尾張旭駅長の横山氏の「出発進行、せーの」の掛け声に続いて、柴田市長、小林統括本部長が「発車」と右手を挙げると、多くのあさぴーや電車のファンに見守られながら、あさぴートレインが出発した。
あさぴートレインは2月末まで運行し、名鉄名古屋本線では、キリンビバレッジ株式会社による紅茶鉄道が12月8日から28日まで運行する。相互に連携しながら、紅茶普及のためのPRを実施する。
この日は13時から尾張旭駅前広場であさぴーの誕生日会が開催され、瀬戸市や小牧市のキャラクター、市内で活動する団体などがお祝いに駆けつけた。
ステージでは、原作者への感謝状贈呈式や、駆けつけたキャラクターによるPR、あさぴーの誕生日をお祝いする歌などが披露された。
各ブースでは、この日のために集まったグッズやメニューなどの販売やあさぴーに贈られた塗り絵の展示などが行われた。また、あさぴートレインと合わせて市内を運行する、あさぴーのステッカーが貼られた名鉄バスの乗車体験なども行われた。
一日を通して、尾張旭駅周辺は多くのあさぴーファンでにぎわいを見せた。
令和6年度尾張旭市政功労者表彰式
令和6年12月1日(日曜日)、文化会館ホール(東大道町)で令和6年度の市政功労者表彰式を実施し、特別市政功労表彰1名、一般表彰(個人)40名、一般表彰(団体)17団体を表彰した。
また、市政の発展に寄与された50名、16団体のかたに感謝状が贈呈された。
式典では、柴田浩市長が「今日の尾張旭市が在るのは、皆様をはじめ、長年に亘る多くの先人の、たゆまぬ努力の賜物であり、市民を代表し、心から敬意を表するとともに、深く感謝申し上げます。私は、本市の良さを、もっと市内外へアピールし、住民にとっては「もっと住みやすい街へ」、それをもう一歩進めて「やっぱり住みたい街」へと変貌させ、子育て世代の方たちにも、終の棲家に選んでもらえるような取組が、本市の未来を切り開く原動力になると考えています。本市のめざすまちの未来像「幸せつむぐ 笑顔あふれる 尾張旭」実現に最善を尽くし、今日よりも明日がもっと輝き、幸せが実感できる街を、市民の皆様とともに創り上げてまいります。尾張旭が、魅力と笑顔にあふれ、市民が誇りを持てる街として、さらなる発展を遂げるよう、皆様には、豊かで貴重なご経験をもって、引き続きのご理解とご協力を賜わりますよう、お願いを申し上げます。」と、これまでの活躍に感謝を述べた。
式への出席者は、81名。