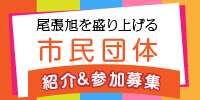本文
国民健康保険税
尾張旭市では、保険料を「国民健康保険税(国保税)」という市税として取り扱い、皆さんが病気やけがををしたときの医療費に使われる大切な財源になります。予測される医療費の総額から、国などの補助金と、医療機関の窓口で皆さんが支払う一部負担金(2~3割)を除いた分が、国民健康保険料(税)になります。納税義務者は世帯主(国保加入者でなくても)のかたです。毎年7月1日に世帯主様宛に納税通知書を発送しますので、納期限までに納付ください。
国民健康保険の計算方法
尾張旭市では、世帯単位で加入者の人数や前年度の所得を医療保険分などの事業ごとにそれぞれ計算し、毎年7月に税額を決定して納税通知書を送付します。計算方法は、市町村により異となります。
税率改定のお知らせ
令和7年度の税率改定は、物価高騰対策として一般会計からの財政支援を受け、引き上げ幅を抑えました。
今後は、国保加入者の減少に伴う保険税収入の減少や1人当たりの医療費の増加、一般会計からの財政支援解消のため、令和8年度以降は、これまでより引き上げ幅が大きくなる可能性があります。
| 国民健康保険税内訳 | 所得割率※1 | 均等割額(被保険者1人につき) | 平等割額(1世帯つき) | 限度額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療保険(基礎)分 | 7.30%(昨年度6.69%) | 27,000円(昨年度26,200円) | 21,600円(昨年度19,500円) | 66万円(昨年度65万円) |
| 2 | 後期高齢者支援金分※2 | 2.87%(昨年度2.67%) | 11,000円(昨年度9,900円) | 8,000円(昨年度6,900円) | 26万円(昨年度24万円) |
| 3 | 介護保険分※3 | 2.31%(昨年度2.42%) | 11,700円(昨年度11,600円) | 5,800円(昨年度6,400円) | 17万円(変更なし) |
※1所得割のもとになる額は、令和6年中の(総所得金額+山林所得金額)-基礎控除(43万円)です。(土地・建物の譲渡所得等も国保税の算定所得に含まれます。)
※2後期高齢者支援金分は、現役世代(0歳から74歳まで)が負担する後期高齢者医療分です。加入している保険の種類にかかわらず、すべての現役世代のかたが負担します。
※3介護保険分は、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当するかたが負担します。
所得の申告について
国保税は、税に関する申告をもとに計算されます。申告がないと、低所得者に該当する場合でも国保税の軽減を受けられません。また、医療費も自己負担限度額が上位所得者として判定されるため、高額療養費の自己負担額が高額になります。適正な保険税の算定や窓口支払いのため、必ず申告をしてください。次に該当する場合でも申告等は必要です。
- 無収入
- 非課税である公的年金等(遺族年金・障害年金等)のみを受給
- 非課税となる失業保険のみを受給
- 給与収入はあるが、勤務先等から給与の支払報告書が出ていない
- 勤務先等から給与の支払報告書は出ているが他の収入もある
- 公的年金以外にも収入がある
- 収入が上場株式の譲渡等のみで特定口座の源泉徴収で申告不要を選択した
国保税の納め方
納付書、口座振替、年金からの天引き(特別徴収)の3種類です。
納付書で納める
市指定の納付書は、市役所、指定金融機関またはコンビニエンスストアで使用できます。また、スマートフォン決済アプリの取り扱い(納付書裏面に記載)を開始しましたのでご利用ください。なお、コンビニエンスストア、スマートフォン決済では「取扱期限」を過ぎた納付書は利用できません。
(指定金融機関)三菱UFJ銀行、あいち銀行、十六銀行、名古屋銀行、瀬戸信用金庫、中日信用金庫、東春信用金庫、東農信用金庫、東海労働金庫、あいち尾藤農業協同組合、愛知・岐阜・三重・静岡各県内のゆうちょ銀行または郵便局
(コンビニエンスストア)セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルオアートナーシップ、ミニストップ、セイコーマート、ポプラ、生活彩家(せいかつさいか)、くらしハウス、コミュニティ・ストア、MMK(マルメディアキオスク設置店)、ハマナスクラブ、スリーエイト
(スマートフォン決済アプリ)paypay、LINEpay、payB、FamiPay、auPAY
口座振替で納める(おすすめします!!)
口座振替は、指定した金融機関の口座から納付期限に自動的に引き落とします。「金融機関などに出掛ける手間が省け」「納め忘れがなく」安全で便利で確実な納付方法です。是非、ご利用ください。
申し込みの手順
- 口座振替依頼書に必要事項を記入
- 通帳届出印を押印
- 市役所または市内にある下記金融機関に提出
申し込みに必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 口座振替依頼書(用紙は市役所または市内にある下記の金融機関にあります。)
- 振替口座の通帳など口座のわかるもの
- 通帳届出印またはキャッシュカード※1
※1キャッシュカードをお持ちの場合は口座振替依頼書を記入をいただき、ペイジー口座振替受付サービスを利用し、キャッシュカード暗証番号を入力いただいての申し込みとなります。この場合は、届出印の押印は不要です。(磁気ストライプ認証の利用できないキャッシュカードおよびあいち尾東農業協同組合はお取り扱いできません。)
口座振替ができる金融機関
三菱UFJ銀行、あいち銀行、十六銀行、名古屋銀行、瀬戸信用金庫、中日信用金庫、東春信用金庫、東農信用金庫、東海労働金庫、あいち尾藤農業協同組合、愛知・岐阜・三重・静岡各県内のゆうちょ銀行または郵便局
国民健康保険税の口座振替 [PDFファイル/209KB](印刷用チラシ)
納付期限(納付書、口座振替による納付)
| 国民健康保険税(令和7年度) | |
|---|---|
| 1期 | 令和7年7月31日 |
| 2期 | 9月1日 |
| 3期 | 9月30日 |
| 4期 | 10月31日 |
| 5期 | 12月1日 |
| 6期 | 12月25日 |
| 7期 | 令和8年2月2日 |
| 8期 | 3月2日 |
| 9期 | 3月31日 |
国保税の特別徴収(年金からの天引き)
65歳から74歳までの国保の世帯主のかたで、次の条件にすべて当てはまる場合は、年金から国保税を手引き(特別徴収)します。申し出により口座振替による納付方法に変更することができます。
- 世帯主が国保の加入者になっていること
- 世帯内の国保加入者全員が65歳から74歳までであること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上あり、国保税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
注意点
※国保税が減額された場合や、特別徴収対象年金が支給停止となった場合は、年度途中で特別徴収(年金天引き)が中止され、納付書等により納めていただきます。それにより、令和8年2月分が特別徴収されない場合は、翌年度4、6、8月分も特別徴収はされません。次回特別徴収になる時期は、翌年度の10月以降からとなります。
※国保税が増額となった場合は、特別徴収する額に変更はありませんが、その増額分については納付書等により納めていただくことになります。
※特別徴収の引き落とし額が(4~8月)と(10~2月)で変わることがあります。
年度の途中で加入や脱退をしたときの国保税
国保税は月割計算となります。途中で国民健康保険に加入した場合は、資格が発生した月から納めることになります。国民健康保険から脱退した場合は、脱退した月の前月までの分を再計算します。加入や脱退の手続きが遅くなると、さかのぼって国保税の納付や還付が発生しますので、忘れず速やかに届け出を出してください。
国保税を納付しないと
保険証の有効期限が短くなったり、保険証の代わりに国民健康保険資格者証が発行される場合があります。資格者証ですと、まず医療費の全額を病院窓口で支払い、市役所窓口で申請後、後日保険診療分の費用を給付します。また、納付が遅れると延滞金が加算されたり、滞納処分を受けることがあります。
所得の低い世帯への国保税の軽減制度や災害、病気、事業の休廃業や失業など特別な事情による減免制度もありますので、納税が難しい場合は、お早めにご相談ください。
相談先:市役所保険医療課(南庁舎1階3番窓口)、市役所収納課(北庁舎1階11番窓口)
納付額確認書
1年間に納付した国民健康保険税の納付確認書を世帯主様宛で毎年1月下旬に送付しています。
事前に金額が確認したい場合は、窓口か電話でお問い合わせください。
国保税の軽減や減免
所得の低い世帯や、災害、病気、事業の休廃業や失業などの特別な事情により税の軽減や減免を受けられます。
低所得世帯のための軽減
国保税は、応能割(所得による担税能力)と応益割(医療を受けるという利益)で成り立っています。所得にかかわらずどなたでも均等割と平等割がかかりますが、世帯の合計所得が基準所得以下であれば、一定の割合で均等割と平等割が減額されます。税申告をもとに計算し、軽減します。
減額の対象となる基準所得と減額割合
- 7割減額 前年中所得43万円+10万円×(給与所得者等※1の数-1)以下
- 5割減額 前年中所得43万円+(30万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数※2))+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
- 2割軽減 前年中所得43万円+(56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数))+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
※1給与所得者数等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受けるかたです。
※2特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の被保険者の資格を喪失したかたのうち、資格を喪失した前日以降、継続して同一の世帯に属するかたです。
非自発的失業者のかたの国保税の軽減
会社の都合による離職など次の(1)~(2)すべてに該当する場合は、申告によりそのかたの前年の給与所得を100分の30として国保税を算定します。この軽減を受けられる期間は、「離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで」で、令和3年度分(令和2年3月31日以降に失業されたかた)まで対象となります。
- 離職日の翌日時点で65歳未満のかた
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または雇用保険の特定理由離職者(雇止めなどによる離職)。雇用保険受給資格者証の第1面にある離職理由コードで確認することができます。
- 特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
- 特定理由離職者 23、33、34
※雇用保険受給資格者証のないかたや、申告をしなかった場合は軽減対象となりません。
※令和2度分の国保税から対象です。国保加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社の健康保険等に加入するなど国保の資格を喪失した場合はその前月までで軽減期間終了となります。
災害や病気、事業の休廃業により世帯の所得が激減したとき
詳しくは、「災害や事業の休廃業などで、国保税や医療費の支払いが困難なときは」のページをご覧ください。
産前産後期間の国保税の軽減
令和6年1月から出産されたかたの産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。
尾張旭市国民健康保険に加入のかたで出産(予定)日が令和5年11月1日以降のかたが対象です。
※「出産」とは妊娠85日以上の分娩をいいます(早産、死産、流産および人工中絶されたかたを含みます)。
対象期間
- 単胎妊娠の場合:出産(予定)日が属する前月から4か月間
- 多胎妊娠の場合:出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間
国保税
国保税のうち出産されるかたの所得割額と均等割額が軽減の対象です・
- 国保税の変更後「国民健康保険税決定(更正)通知書」が送付されます。
- 軽減により、国保税の納めすぎがある場合は、後日還付のお知らせが送付されます。
- 軽減後も国保税の限度額を超えている場合は、国保税は変更されません。
届出に必要なもの
- 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
- 出産予定日のわかる書類(母子手帳など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 別世帯のかたが届出する場合は、世帯主からの委任状
出産予定日より6か月前から届出できます。
※出産育児一時金(直接支払制度)の支給を受ける場合は、届出不要です。
後期高齢者医療制度の創設に伴う国保税の緩和措置
「特定同一世帯所属者」世帯に対しての措置
同じ世帯の中に、後期高齢者医療制度への移行により国保を脱退したかたがいる場合
- 国保税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
- 国保加入者が後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の国保加入者が1人となる場合は、平等割が5年間半額になり、その後3年間は4分の3になります。
旧被扶養者に対しての措置
75歳以上のかたが会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であったかた(65歳以上のかたに限る)が新たに国保に加入することになる場合の措置です。
(平成31年4月より、下の2,3は資格取得日から2年間適用となりました。)
- 所得割額が免除になります。
- 均等割が半額になります。(7割・5割軽減に当てはまらない場合)
- 旧被扶養者のみの世帯は平等割が半額になります。(7割・5割軽減に当てはまらない場合
国民健康保険税の財源が不足 国保税率見直しにご理解を
税率見直しについて
国民健康保険税は、県内統一の算定基準(標準保険料率)と同等になるよう令和3年度から見直しています。令和7年度の税率改定は、物価高騰対策として一般会計からの財政支援を受け、引き上げ幅を抑えました。今後は、国保加入者の減少に伴う保険税収入の減少や、1人当たりの医療費の増加、一般会計からの財政支援解消のため、令和8年度以降はこれまでより引き上げ幅が大きくなる可能性があります。
| 項目 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|
| 歳入 | 70億3,636万円 | 70億 749万円 | 71億3,707万円 |
| 歳出 | 70億 873万円 | 70億4,822万円 | 71億 921万円 |
| 歳入ー歳出 | 2,764万円 | △4,073万円(赤字決算) | 2,786万円 |